
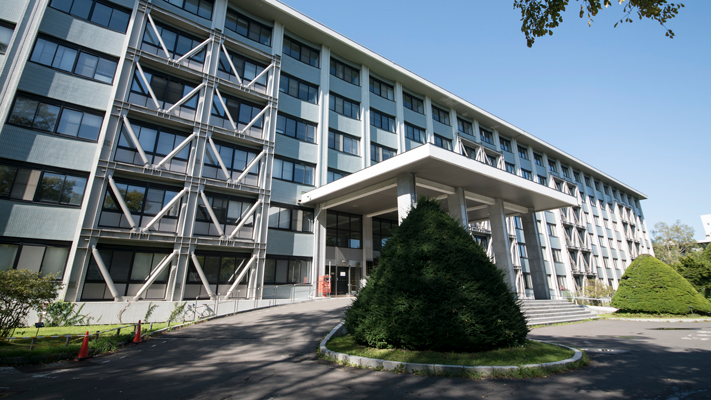

大学院工学研究院長
教授 幅﨑 浩樹
Prof. Hiroki HABAZAKI
北海道大学大学院工学研究院は,北海道大学の学院研究院構想に基づき,2010年に大学院工学研究科を大学院組織である工学院と総合化学院,教員組織である工学研究院に改組することで設置されております。2020年の改組を経て現在は9部門と1附属研究センターから構成されています。さらに本学が強みを有する研究分野の推進を担う組織としてフロンティア化学教育研究センター(FCC),f3工学教育研究センター,原子力安全先端研究・教育センターが設置されており,人材育成面では,工学系教育研究センター(CEED)が,各省庁と連携した科学技術政策に関する講義や海外インターンシップ,e-leaning教材開発などにおいて多くの実績を上げております。工学研究院は約300名の研究者を要しており,材料・化学を中心とするフロンティア研究および北海道の優れた環境を生かしたフィールド研究を研究の強みとしており,2022年のTHE (Times Higher Education)インパクトランキングで北海道大学が国内1位(世界10位)となったSGDsの取組にも大いに貢献しています。
情報通信技術等の急速な発展に伴い,産業・経済・社会の大きな変革期を迎えている中,2050年のカーボンニュートラルの実現,少子高齢化対策,感染症や大規模自然災害に強い社会の実現などに対応するために,多様な知の集積によるイノベーションの達成が必要となってきています。日本全国そして世界各国から多様な人材が集っている総合大学である北海道大学の特色を生かし,各分野で先導する研究を推進している研究者の知の融合により,新たな研究分野の開拓とそれを社会・産業変革へとつなげていくことが望まれています。そのような中,工学研究院では計算科学,情報科学,実験科学の3分野融合を進め,物質創製の革新を図る「化学反応創成研究拠点」(WPI-ICReDD),先進技術を導入して農林水産業の革新を図ることを目的として農学研究院や水産科学研究院等と連携した「ロバスト農林水産工学国際連携研究教育拠点」,鉄筋コンクリートに代わる次世代材料「ロジックス構造材」研究開発事業,次世代型航空宇宙産業の創出を目指す室蘭工業大学等と連携した「”F3(エフキューブ)工学”教育研究拠点」などの異分野連携教育研究拠点事業を実施しており,今後も複雑かつグローバルな難課題の解決と地域・社会への貢献を目指した知の集積に工学研究院内に留まらず,学内,他大学・他研究機関,産業界や自治体と連携して取り組んでいきます。また,そのような活動を通して,次世代の知のプロフェッショナルとなり,未来社会をけん引する人材の育成にも一層努めてまいります。

大学院工学院長
教授 泉 典洋
Prof. Norihiro IZUMI
来れ、北大工学院へ!
いま、人類はかつてなかったような危機に直面しています。未知の病原体による感染症のパンデミックは世界を混乱に陥れました。国際社会の現状を力で変更しようと試みる一部の国家が、当事国のみならず世界の安全保障を脅かしています。某国では、民主主義がその危うさを露呈し、世界では権威主義国家や独裁体制国家が台頭しています。多様性に不寛容な一部の国では、いまだに女性やマイノリティが不当な差別を受けています。先進国で少子高齢化が進む一方、発展途上国では大幅な人口増加によって、貧富の格差がますます広がっています。自然環境を犠牲にした経済発展は、地球温暖化とそれによる気象災害の激甚化を引き起こしています。
これらの問題のほとんどは、一見すると工学とは関係ないように思えるかも知れません。もちろん、工学の成果のみを持ってしてこれらを解決することはできないでしょう。しかし、工学の成果が解決への一助となる問題も少なくありません。これらの問題は、往々にして数多くの複層的な要因が多次元的に作用し合うことで生じています。何らかの工学上の技術的な障壁が問題を生む要因の一つとなっていることも少なくないのです。ただし、工学の成果を役立てるためには、工学の知識だけでは不十分です。一つの分野に関する深い知識と高い問題解決能力だけでなく、文系まで含めた様々な分野に関する幅広い知識を持ち、それらを組み合わせる柔軟な思考力や豊かな想像力が必要となるのです。
工学院は、工学系の修士課程と博士後期課程からなる大学院です。工学部では十分な専門的知識が身に付かなかったと感じて工学院へ進学する学生も多いことでしょう。しかし、工学院に進学したら専門の勉強に加えて、専門外の講義を取ることで多様な知識を身につけると同時に、その他の様々な能力を磨いて欲しいと思います。修士課程で研究に頑張れば、国内外の学会で研究成果を発表し、同様の研究をしている海外の学生や研究者と話をする機会にも恵まれるでしょう。それによって、国際的なコミュニケーション能力や世界に向けた広い視野など、学部では得ることのできない高いレベルの知性を身に付けることができます。さらに博士後期課程では、そのような機会は一段と多くなります。最先端の研究に接したり国際的に一流の人達と会話をしたりする中で、幅広い知識だけでなく深い教養を身に付けることができます(身につけないと会話ができないのですから)。研究室の運営を任せられている間に、組織をマネジメントする能力も身に付くことでしょう。博士課程では修士より一段と高いレベルの知性が身に付くのです。
いまや、世界の先進諸国の中で日本における博士の学位を持った人の割合は最低レベルです。日本はいつの間にか低学歴社会となってしまいました。それが、現在の日本経済の停滞やイノベーション力の低下の原因だとも言われています。海外の企業の幹部や国際連合の職員の多くは博士です。また、欧米で起業する人達の多くが博士の学位を持っています。もし、世界で、あるいは国際的な舞台で活躍したい、日本のイノベーションを引っ張って日本経済の再生に貢献したいという気持ちがあるのであれば、是非、博士課程に進学して下さい。
工学院では、高い知性以外に、もう一つ重要なものを身に付けて欲しいと思っています。それは、一朝一夕には学べない、そして言葉になりにくい、夢とか理想あるいは哲学とか品性、そういうものから生まれる何かです。それを身に付けて初めて、目的や価値を正しく判断し、知性を人類にとって正しい方向に使うことができるのです。かのアインシュタインは、原爆の開発に貢献した自分に対する自戒の意味を込めてこう言っています。「知性とは、方法や手段に対して鋭い鑑識眼を持っているが、目的や価値に対して盲目である」と。
諸君、北大工学院に来て、高い知性と目的や価値に対する正しい鑑識眼を身に付けた人となって下さい。待っています。

