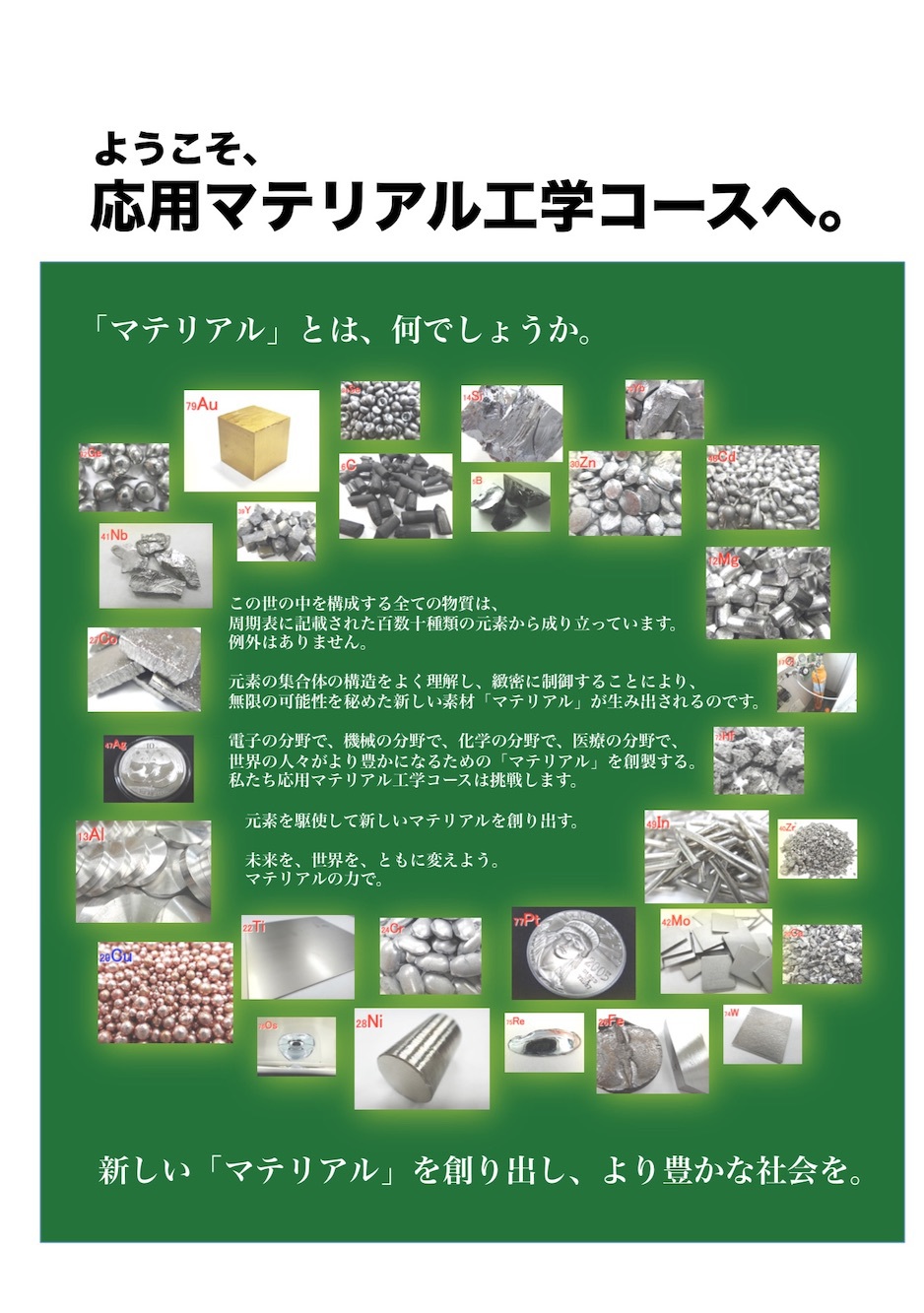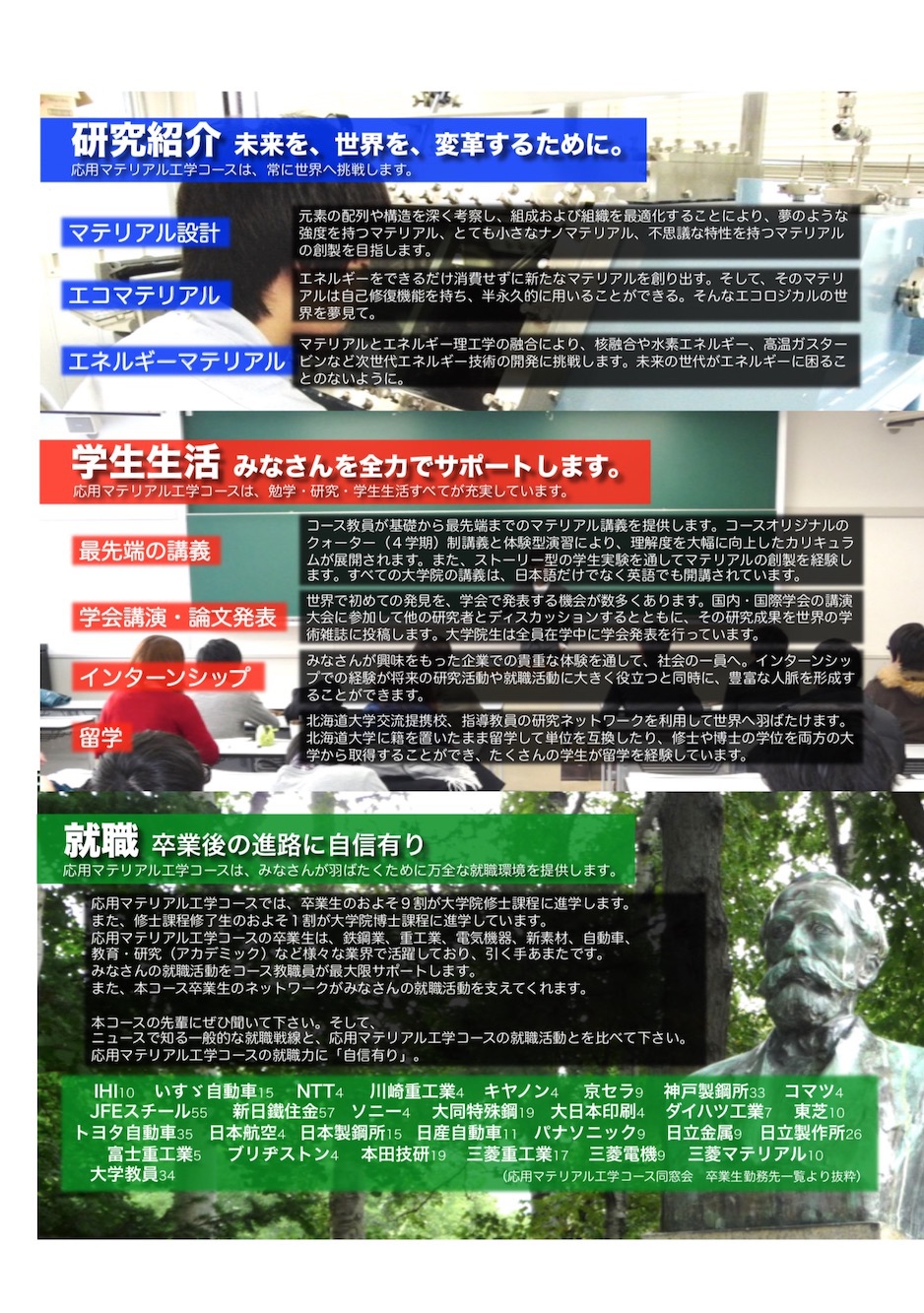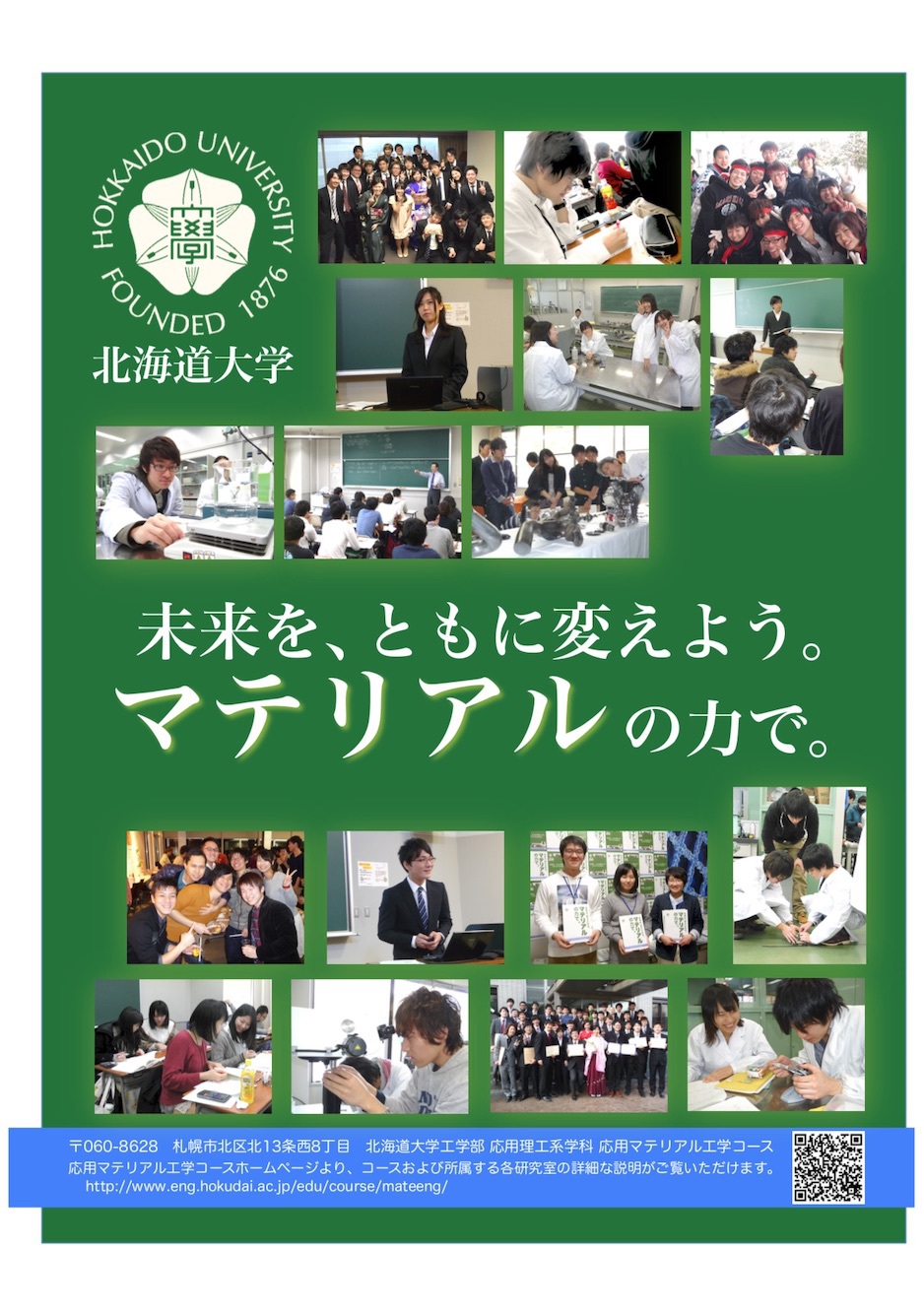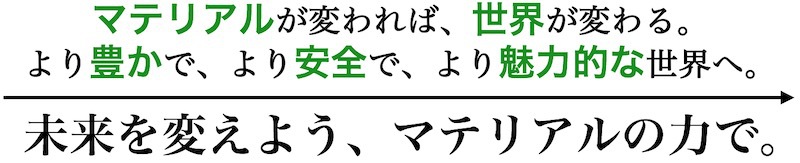


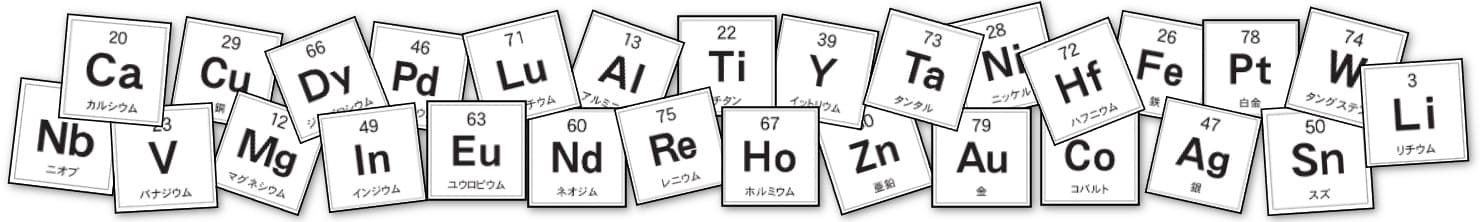
こちらは、学部4年生の卒業論文題目一覧です。
水素、CO2分離、太陽光エネルギー、高温特性、光触媒、蓄光体、電子顕微鏡、ハイエントロピー合金、磁場・振動印加、計算科学、イオン液体、潜熱蓄熱、燃料電池などをキーワードとして、幅広い金属・半導体・酸化物材料の科学(マテリアルサイエンス)に関する研究を行っていることがおわかりいただけると思います。
1. 液相燃焼合成製MnドープSrTiO3光触媒の特性評価
2. 画像解析によるインフラ腐食診断のためのデータ構築
3. Cu64Oナノ粒子の合成及び導電性インクペーストへの応用
4. 鋳壁から発達したデンドライトへ振動印加したときの挙動
5. 高速AFMを用いた電位変化によるPEG吸着現象のその場観察
6. Ni-Al合金におけるNi固溶体の核生成の分子動力学シミュレーション
7. 水素ポンピングを活用した電気化学的CO2分離法の研究
8. サブミリスケール力学試験実現のための試験片作製手法及び試験系の確立
9. Cu,Ni錯体を用いた導電性インクの作製
10. 金属電極とPTFEからなる水滴発電機の作製と高出力化
11. 尿素・グリシン混合燃料を用いた液相燃焼合成によるSr9Al6O18:Sm3+蓄光体の作製
12. 基板上に分散したPt原子拡散挙動のHAADF-STEM観察
13. 塩化水素を含む高温水蒸気雰囲気中におけるマルテンサイト系ステンレス鋼の高温腐食挙動
14. 金属積層造形法により作製した316L及びFCC型ハイエントロピー合金の評価
15. 第一原理計算を用いたα-Al2O3/α-Cr2O3界面における水素同位体の安定性と拡散特性の評価
16. 減圧環境のNaf2N系イオン液体におけるNaの高純度化
17. 炭素鋼の大気腐食による電位と水素透過電流の同時計測
18. Al2O3形成耐熱オーステナイト鋼の高温酸化挙動に及ぼすTiの影響
19. Al-Mg-Si系合金の時効析出がクリープ変形挙動に及ぼす影響
20. EmImBF4含有EmImCl-AlCl3イオン液体からのAl電析
21. Ti-X(X=B,C)基セラミックスの燃焼合成反応を利用したアルミニウム合金粉末床の急速加熱
22. 機械学習を用いた一次元拡散過程の逆問題解析
23. 種々のリン酸塩電解質を用いたアルミニウム陽極酸化皮膜のナノ構造制御
24. 充填層型潜熱蓄熱装置の性能調査
25. Phase Field 法を用いた圧縮応力下におけるキンク組織成長のシミュレーション
26. 酸化物分散強化ハイエントロピー合金の創製
27. CuOナノワイヤーメッシュを用いた太陽光水蒸発の基礎的調査
28. CoフリーFCC型ハイエントロピー合金の特性評価
29. EmImCl-FeCl3イオン液体からのFe電析
30. 第一原理計算を用いたTi系MXeneのエッチングプロセスの理論的研究
31. 可逆作動可能な固体酸化物燃料電池用電極材料としてのLa1-XSrXFeO3-δの液相燃焼合成
32. 軽量ハイエントロピー合金の水素吸放出特性評価
33. 水熱および水中光合成法による各種タングステン酸ナノ結晶の作製
34. 磁場中スリップキャストを用いた配向Ti2AlC焼結体の作製と異方性の評価
35. 不均一濃度場における第二相粒子の成長挙動の数値解析
36. 軽量ハイエントロピー合金の酸化特性評価
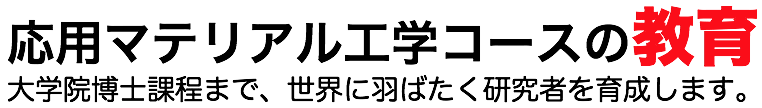
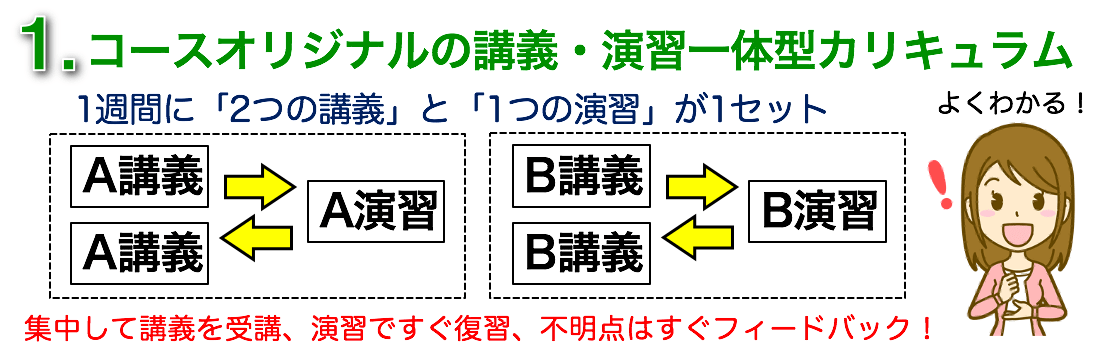
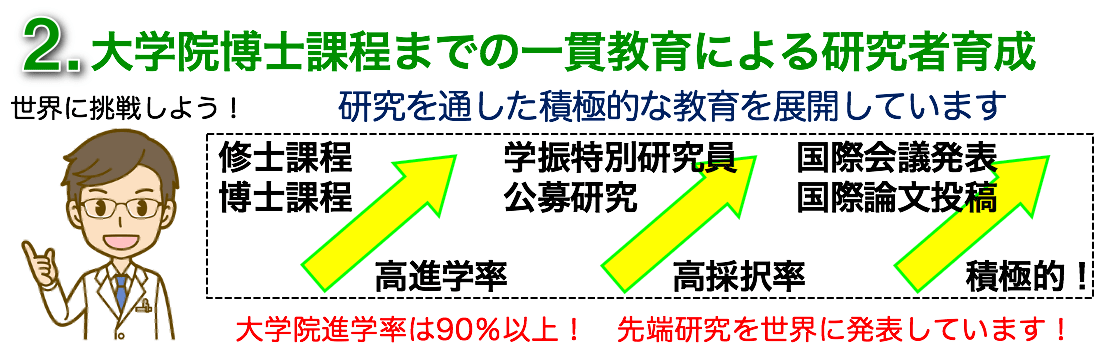
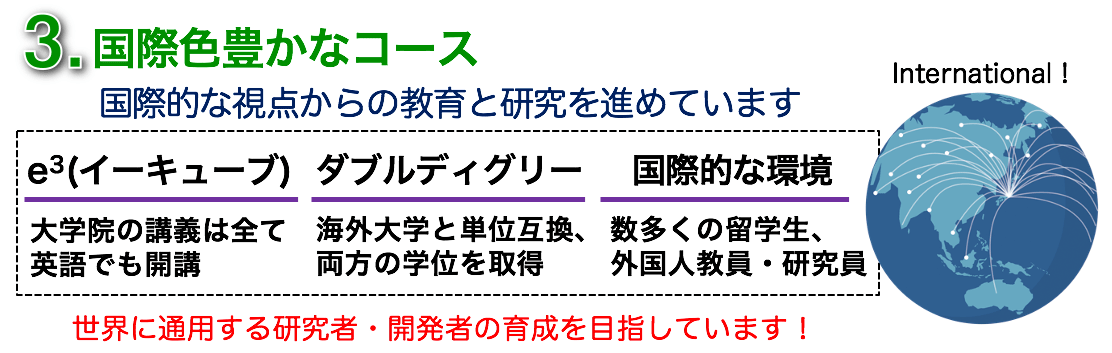
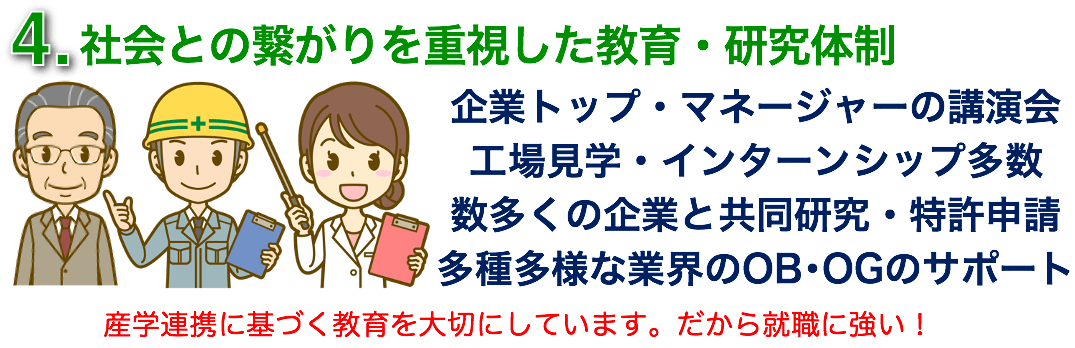
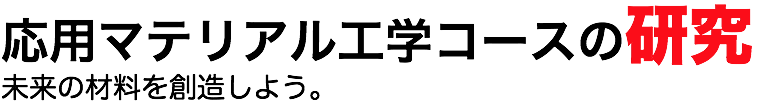
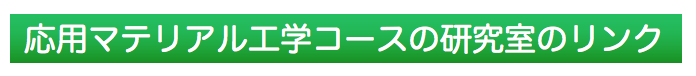
生産量数百万トンの巨大な鉄鋼製造プロセスから、新材料の創生を可能にするマイクロスケールプロセスまで、その成否は運動量、熱および物質移動の精密なコントロールにあります。電磁場や超音波などの新規なツールを用いたプロセスの研究を通して、この命題解決に取り組んでいます。
キーワードは「電気化学を用いた材料表面科学」。電気化学の力を用いて材料表面の微細構造を自由に制御することにより、革新的な特性を生み出す研究を進めています。材料の表面が変われば、材料の全てが変わる。
【主な研究テーマ】●自己規則化ナノマテリアルの創製 ●高速超親水・滑落性制御型超撥水・超撥油表面の構築 ●ナノ構造の最適化によるサステイナブルな材料の設計 ●降雨を利用した水滴発電機の開発 ●持続可能な貴金属リサイクル技術の開発
光を使って表面をナノスケールで観察し、耐食性表面や反応界面における微細な構造を明らかにします。レアメタルなどのリサイクルや高純度化プロセスを考え、国内における金属資源の循環を目指します。
環境に優しい社会の実現に貢献するために、1500°C級超耐熱合金や軽量高強度合金などを開発しています。物性と組織、組織と合金組成の関係の『実験的』追求と『理論的』理解より、未来の社会に求められる合金開発を目指した組織設計・組成設計を確立します。
鉄鋼材料や非鉄金属材料の高性能化、高機能化、高品質化を目指し、理論・実験・計算・データ科学のアプローチを使って材料組織学の最先端を切り開く研究を行っています。特に、計算材料科学によって構造材料を構成するナノ・ミクロの多様な組織を理解・制御することに取り組んでいます。
【主な研究テーマ】●材料組織の数理モデリングと計算機シミュレーション ●データ同化によるパラメータ推定 ●マクロ偏析シミュレーション・モデルの高精度化・高速化 ●分子動力学法による材料組織の解析
材料の表面・界面を原子レベルで制御して、新しい材料を創り、日本の産業基盤の強化に努めています。 例えばこれまでに世界になかった新しい金属クラスターを設計・合成し、世界に提案します。また、新規なナノ材料の設計と構造制御、特に合金系など複雑な微細構造をもつナノ材料を創ります。そして、こうした材料の示す特異な機能を見出します。また、材料の表面および界面の特性を解明し、材料の特性の変化、環境の及ぼす材料への影響を解明し、よりエコロジカルな材料活用法を見出します。
【主な研究テーマ】●新規金属ナノ材料の合成と新しい機能の発現 ●酸化しない遷移金属ナノ粒子の合成と電子部品部材への応用展開 ●ナノ材料のバイオ分野ならびに質量分析分野への応用展開 ●溶液フロー型微小液滴セルによる新材料設計と材料改質 ●金属の腐食挙動の詳細解明と実材料への応用展開 ●革新的金属空気電池の開発
材料の本来の機能•特性の発現とその実用化をテーマに掲げ、高エネルギー粒子線を用いた材料の微細構造変化の評価や高い照射耐性を有する材料の創製及び高機能化、また水素エネルギ一社会に対応可能な水素貯蔵材料のナノ構造や非平衡相形成に関して、電子顕微鏡をはじめとする最新の各種分析機器を用いた研究を行い、得られた基礎的知見を材料開発及び改良に役立てています。
耐酸化性と高温強度を両立する耐熱合金の開発、過酷な環境下で用いられる耐熱合金やコーティングの耐腐食性向上、高温強度/耐酸化性/耐照射性を有する酸化物分散強化型(ODS)合金の研究開発を行っています。材料組織学、熱力学や速度論などの材料科学をベースに、高温強度と耐環境性を両立させた先進エネルギー材料の創製を目指します。
【主な研究テーマ】●航空機用Ni基合金の耐高温腐食性の向上 ●耐高温エロージョンコロージョン特性に優れるコーティングの開発 ●保護性アルミナ皮膜の特性向上手法の開発 ●オーステナイト系耐熱鋼の開発 ●廃棄物発電ボイラの過熱器チューブの耐塩化腐食性向上 ●酸化皮膜中に発生する残留応力の測定とその起源 ●耐熱アルミニウム合金の表面処理による高温強度向上
エネルギー利用の高効率化とそのためのマテリアル開発基盤を構築するため、原子レベルの構造評価、ナノ計測技術、計算機シミュレーションを組み合わせ、材料のナノからマクロまでの特性とその起源をマルチスケールで解析・評価しています。特に,先進電子顕微鏡を活用した「材料解析手法の開発」、蛍光体や酸素吸蔵材料、水素遮蔽用保護被膜などの「機能性セラミックスの開発」、燃料電池電極触媒や(脱)水素化触媒などの「省貴金属化」に関する研究を中心に推進し、各種プロセスの省エネルギー化や水素エネルギー社会の実現に貢献しています。
物質の多様な物性を材料科学の立場から最大限に活用し、高効率で低環境負荷な光エネルギー変換、 熱電エネルギー変換のための高度な機能を持つ新しい材料の開発創製研究を進めています。なかでも太陽電池や発光素子などの光電変換、光触媒・光反応効果の特性を有する光デバイス材料創製や高効率の熱電材料開発など、ナノ構造に由来する新規機能材料の創出を目的としています。
【主な研究テーマ】●光反応の材料科学基礎 ●光誘起ナノ材料創製(結晶光合成) ●光電変換材料のナノ科学 ●微細構造制御による熱電材料の性能向上 ●酸化物熱電材料の非化学量 論制御と輸送特性の評価
ホメオスタシス社会の創製を究極の目的として、エネルギーを高密度に貯蔵、輸送、高効率に変換する材料の開発を行うとともに、エクセルギー理論によるシステムの評価・設計を行っています。
【主な研究テーマ】●次世代製鉄プロセスの開発 ●潜熱蓄熱を基盤とした次世代蓄熱・熱輸送・熱制御技術の開発 ●各種機能性材料の燃焼合成と特性評価 ●エコ・コンビナート設計
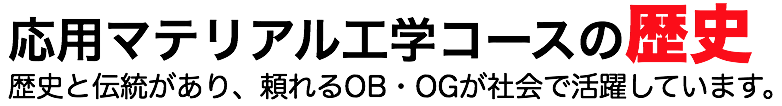
昭和17年(1942年)4月7日
北海道帝国大学工学部に生産冶金工学科が設置された(現・応用マテリアル工学コースの誕生)。