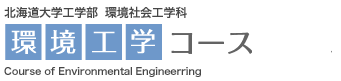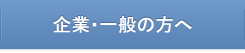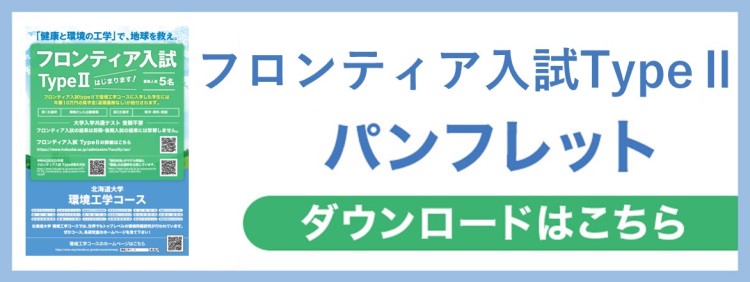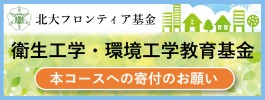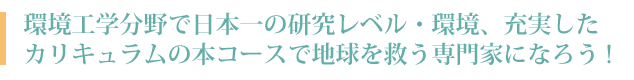
先進国でも途上国でも、環境問題の重要性はますます高まっている。 今、この時代こそ我々衛生環境工学の出番だ。 世界中に飛び出し、「生(いのち)を衛(まも)る工学」で地球を救おう。
人類の利便性に偏重した開発を続けてきた代償として、社会の安全性や環境の持続可能性が大きく揺らいでいます。革新的な環境浄化技術、省エネルギー技術、資源循環技術への社会的要請はこれまでになく高まっています。また、人間の健康、健全な環境をどのように評価するのかについても、本コースが答えを出さなければなりません。
環境問題は複雑化と広域化を続けており、絵空事ではない循環型社会システムの構築と実践が急務となっています。環境問題が内包する公共性は君たちの倫理観を、国境を超える多様な問題は君たちの国際性を否応なしに磨きます。様々なスケールで問題を洞察し、国際的な舞台で推進力を発揮できる人材の育成を本コースでは目指しています。
|
環境問題の解決へより直接的に貢献したい、関わる仕事に就きたいと希望している人に最適なコースです。環境問題の研究では、広い分野の先端技術と知識を高度に統合する必要があります。知的好奇心の旺盛な人、異分野横断研究を推進する行動力のある人を歓迎します。行政他の立場で公共のために働きたいと願っている人。国際的に活躍してみたいという夢を持っている人。最先端の科学を応用した新技術を開発したいという熱意のある人。異分野・異文化の人々と積極的に交わり、環境問題の解決に新しい道筋をつける意欲のある人。新しい社会の枠組みを提案したいという「大志」を抱いている人。きっと、我々のコースで良い出会いが待っています。 |
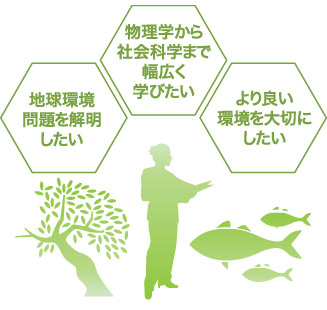 |
※平成18年度には2012年ノーベル医学生理学賞受賞の山中伸弥教授が受賞している。
2012〜2022年度:全2件のうち、本コース2件。
2018〜2022年度:全15件のうち、本コース7件、東北大3件、東大2件、京大、広島大、岐阜大 各1件。
平成29年度において、科学研究費助成事業※の321の研究分野の中で北大の新規採択件数(過去5年累計)が全国一位である研究分野は7つでしたが、この内2つは北大・環境工学コースに関連している土木環境システム と 環境技術・環境負荷低減 でした。このことより、北大・環境工学コースは日本でトップレベルの環境工学の研究グループであると解釈できます。
・学生ポスター発表賞(ライオン賞)、優秀発表賞(クリタ賞)
2018〜2022年度の間、ライオン賞全84件のうち本コース10件、クリタ賞全82件のうち本コース23件で両賞ともに受賞数がトップでした。
・論文奨励賞、優秀ポスター発表賞、環境技術・プロジェクト賞
・優秀ポスター賞
・優秀ポスター賞
・The WET Excellent Presentation Award
・Best Paper Award
 |
岡部 聡 教授
地球上には様々な生物が相互に微妙な生態系バランスを保ちながら存在しています。地球規模の炭素や窒素循環は、目に見えない小さな微生物が駆動しています。しかし現在、我々人間の活動や地球温暖化などにより地球規模で生物多様性が急速に失われています。このような環境の中で生態系を構成する生物の1種として、どのようにふるまわなければならないか?を理解するためには、生命の誕生、進化、そして生物の種と機能の多様性とその重要性を理解する必要があると思います。私は微生物(工)学を中心に教育研究をしています。環境にやさしいバイオ技術で私たちのかけがえのない地球環境を保全・改善していきたいと思います。皆さんも一緒にチャレンジしませんか?
|
 |
石井 一英 教授
私たちは早く産まれたという理由だけで無意識に限りある資源を利用し、かけがえのない環境に悪影響を与えています。また、日本という先進国に産まれたという理由だけで、貧しい発展途上国から無意識に資源を搾取しています。すなわち、3つの弱者(環境、発展途上国、次世代)との共生を図っていく必要があります。本コースで、問題解決の視点から環境を適切に診断し改善するため基礎能力(分析・解析・評価)及び未来の環境を創る能力(ビジョン構築、計画策定、市民参加)の両面を学んで、共生を実現するための社会イノベーションを巻き起こす多様な専門家になって欲しいと思います。
|
 |
長野 克則 教授
空気・水・熱。それは、生きていくのに一瞬たりとも欠かせないもの。これら生活に密着したものが我々の研究対象であり、学びや研究のスケールは大地、海洋、大気、太陽と地球規模です。私も本コース出身ですが「地球の受容量は無限ではない」ことを常に意識すること、つまり、自分が出したものがどう辿るのかを考えることが教えの根源です。例えば、建物から排出する二酸化炭素、これを最小にするにはまず建物の断熱強化や換気熱回収などによる徹底したローエネルギー化が重要であり、その上で再生可能エネルギーによる電力と熱の供給を行うのです。外も内も安全で持続可能な生活空間の創造、そして地球と人間が共に健康で気持ちよく生きていく世界を考え、共に学んでいきましょう。
|