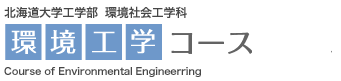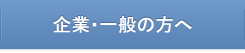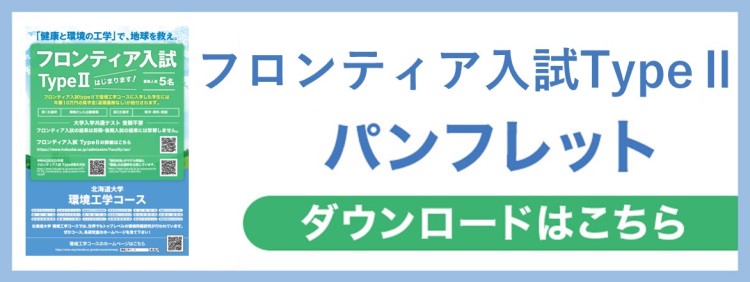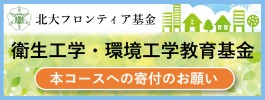1. 水質変換工学研究室
微生物は地球環境のあらゆる場面でかけがえのない重要な役割を担っていますが、同時に大規模な感染症などの大きな災厄をもたらすこともあります。本研究室では、この微生物の働きに着目し、”水環境バイオテクノロジー分野”を開拓することで”美しくかけがえのない水環境”をいつまでも守ることを目標としています。
2. サニテーション工学研究室
我々が排出する下水の中には、植物の栄養源となる窒素やリンをはじめとした様々な資源が含まれています。大量のエネルギーをわざわざ注入し、資源を汚濁物の形で水環境へ排出している現在の下水処理から、資源やエネルギーを下水より回収できる新しいシステムへ転換するための研究を行っています。
発展途上国でも普及させられるトイレの開発、水再利用に直結する膜を用いた水処理に関する研究などが活発に行われています。
3. 水環境保全工学研究室
きれいな川、湖、海を世界中に残したい。そんな想いから、私たちの研究室では国内外の自然を調査する、誰でも簡単に水の汚れを測定できるセンサーを作る、発展途上国でも安く排水を処理できる技術を作る、といった事に日々チャレンジしています。発展途上国に貢献できます。自然の調査は極上のアウトドアです。センサー作りは工作や料理と同じ楽しさがあります。好奇心あふれる方、一緒に研究しましょう。
4. 環境人間工学研究室
人間が生物として持つ特性を正しく理解し、その特性のうち生理的特性が生活習慣や生活環境にどのような影響を受けるのか?その影響は適応的なのか?に興味を持ち研究を行っています。そして、現代を生きる人間にとって、「健康」で「快適」な環境の構築を目指しています。
5. 環境システム工学研究室
自然エネルギーの活用、高効率複合エネルギーシステム、環境負荷低減テクノロジー、また良好な室内環境、安全な労働産業環境の創造など、 健康で持続可能な社会の実現に向けて、都市のエネルギー消費と生活環境問題の解決に取り組んでいます。
7. 廃棄物処分工学研究室
ごみは家庭、事業所、産業などすべての社会活動から生み出され、有害物や有用な資源を含めたさまざまな廃棄物を、適切に処理、処分、あるいはリサイクルしなければなりません。ごみの範囲は広く、そして解決を必要とする新しい問題が次々に現れます。私たちは、ごみ処理全般にわたって、化学分析、実験、現場調査などのハード面とアンケート、データ分析のソフト面での手法を用い、社会が必要とする研究を進めています。
8. 地域環境研究室
大気中に存在する微量物質が、どの程度存在するのか?どのように輸送、反応・沈着するか?どう影響するか?どう制御すべきか?を「地球上の物質循環」という視点から考えています。研究はフィールド観測(離島、極域、都市での大気観測)、観測装置の開発、コンピュータによる解析など多岐にわたっています。
9. 環境リスク工学研究室
ナノスケール微粒子を用い、次世代型の浄水処理技術を開発するとともに、既存、新規水処理技術の評価を行う事を目指します。 基礎研究のみならず、その実用化までを視野に入れるとともに、環境政策に密接につながった研究を薦め、政策への提言を発し続けます。
10. 循環計画システム研究室(寄付講座:エコセーフエナジー分野)
循環型共生社会の実現のために、住民参加のもと、廃棄物を減らし、リサイクルを促進し、その後適正処理する循環計画を、システムとして合理的に策定する必要がある。我々の研究室の目的は、この実現を社会使命として、臨床的なアプローチとシステム工学的・社会経済的な手法を用い、廃棄物等の適正な物流・変換を計画・設計・維持管理する社会技術システムを合理的に構築することである。
また、寄附分野の「エコセーフエナジー」分野とは密接に連携し、再生可能エネルギーとしてのバイオエネルギーの普及促進による、環境に配慮したエネルギーの地域自立・分散型システムの開発を目指している。
本コースでは、「衛生工学・環境工学教育基金」を立ち上げました。
新入試制度(フロンティア入試タイプII)により環境工学コースに入学した学生への奨学金給付、および学部教育用設備の更新や博士後期課程に在籍する学生への経済的支援などに有効に活用させていただきます。
中島芽梨さん、佐藤久教授(水環境保全工学研究室)と、産業技術総合研究所、海洋研究開発機構、東北大学の研究グループが、メタン生成アーキアに寄生する超微小バクテリアの培養に成功した研究論文について、プレスリリースを行いました。
北島正章准教授(水質変換工学研究室)が、新型コロナウイルスの下水調査に関して、複数のテレビ番組、新聞等に登場しています。
石井一英教授(循環共生システム研究室)が、株式会社クボタ様作成の『2050年未来会議「食料・水・環境」を本気で考える』(Newspicksのネット番組)に出演しました。
北島正章准教授(水質変換工学研究室)らの研究グループが、下水中の新型コロナウイルス濃度が医療機関における感染者数の指標になることを証明し、本研究論文についてプレスリリースを行いました。
中屋佑紀助教(水環境保全工学研究室)が、環境工学研究フォーラムにて環境技術・プロジェクト賞を受賞しました。
Mohomed Shayan君(水環境保全工学研究室)が、The Water and Environment Technology ConferenceにてWET Excellent Presentation Awardを受賞しました。
Hyungmin Choi君(水質変換工学研究室)が、The Water and Environment Technology ConferenceにてWET Excellent Presentation Awardを受賞しました。
池田澪さん(水質変換工学研究室)が、Asian Symposium on Microbial EcologyにてPoster Awardを受賞しました。