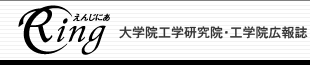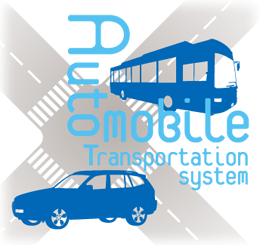
20世紀は自動車文明の時代でした。
化石燃料を使用した自動車を中心とした交通システムが産業の発展や社会の安定を支え、文化の交流を促しました。
しかしながら交通事故、交通渋滞、環境汚染など自動車交通による"負の遺産"の解決が、21世紀に委ねられています。
昨年度、中国の自動車販売台数が世界一となりました。
他のアジア各国における自動車台数の増加も目覚ましいものがあります。
世界各国の自動車の保有意欲を満足させながらも環境に優しい技術を確立するための大きなパラダイム変革が求められているのです。
わが国では、昨年の交通事故死者数が5千人を下回り、 ピーク時の4分の1近くに減少することに成功しました。
交通安全対策の成功事例として世界からも高く評価されています。
ところが、その中で歩行者の割合は約3分の1も占め、欧米諸国の約2倍です。
歩道の設置など時間と費用を要するハードの施設整備に替わるソフト技術による対策も求められています。
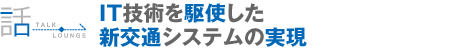
〉〉 環境に優しい自動車へ
今、電気自動車や水素自動車が化石燃料自動車に替わると注目されていますが、技術的問題や費用など課題が多く、その実現にはまだ時間を要すると予想されています。欧州では、温暖化対策への切り札としてディーゼルエンジン自動車が多く用いられています。同時に、将来の燃料電池の挙動特性に関する基礎研究や、エネルギーシステムの観点から考える最適な将来型自動車形態に関する研究も重要となっています。
〉〉インフラライトな交通システムへ
近年のIT技術を活用し交通データとして使えるものは何でも利用し、的確な交通情報を提供できれば、交通渋滞を緩和することが可能になります。冬期の路面状態に関するリアルタイム情報と地域住民の連携によって歩行者事故を防止する、あるいは歩行者の挙動を関知して運転者への安全運転支援を行うなど、従来のハードな施設整備から情報を中心としたソフトな交通システムへの挑戦が行われています。
(コーディネーター 中辻 隆)
 最もエコなパワーソース、
最もエコなパワーソース、
それはディーゼルエンジン
エネルギー環境システム部門
応用熱工学研究室
教授 小川 英之 データ融合技法に基づく
データ融合技法に基づく
動的交通制御システム
北方圏環境政策工学部門
交通インテリジェンス研究室
教授 中辻 隆 冬期つるつる路面を
冬期つるつる路面を
市民の協働とIT技術で克服する
北方圏環境政策工学部門
建設管理工学研究室
准教授 高野 伸栄
 燃料電池内現象解明と
燃料電池内現象解明と
将来自動車構成分析
エネルギー環境システム部門
エネルギー変換システム研究室
教授 近久 武美、准教授 田部 豊 歩行者を自動車事故から
歩行者を自動車事故から
守るシステムの開発
大学院公共政策学連携研究部公共政策学部門(大学院工学院 北方圏環境政策工学専攻建設管理工学研究室 担当)
教授 萩原 亨