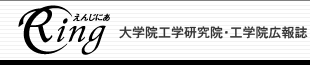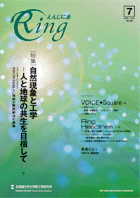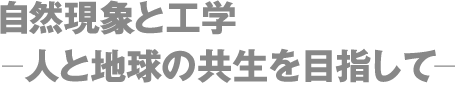
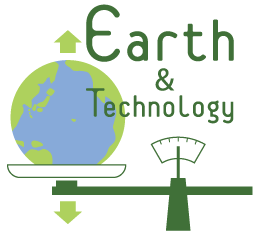
地球は46億年前に誕生しましたが、人類の登場はわずか200万年前です。46億年の地球の歴史を1年と考えると人類の登場は12月31日の午後10時頃になります。しかし、この短い期間に人類は65億人にまで増加し、その活動によって地球温暖化や酸性雨などを引き起こして地球の環境そのものを危うくしており、その対策が急がれています。一方で、これまで人類は、さまざまな方法によって地震や津波、火山爆発、台風などの自然災害と向き合ってきました。今回は、地球環境汚染や自然災害に対して、その解決をはかり地球との共生を目指している工学研究を紹介します。
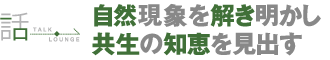
〉〉メカニズムの正しい理解が難問解決の基礎
新しいものを作るため、あるいは環境問題の解決や自然災害への対処のためには、自然現象を正しく理解することが不可欠です。たとえば、雨滴が生成される仕組みや、雲の中を飛ぶ航空機に氷が付着する仕組み、ビーチに達した波の状態のほか、最近工業化が著しい中国地域から日本に、黄砂とともにどのような汚染粒子が運ばれて来るのか。強い地震の発生原因やその波(地震動)の伝わり方、土砂崩れの起こりやすい地盤とは? これらのメカニズムを正しく理解することが、諸問題解決のための基礎となります。
〉〉早めの対策が地球環境や防災・減災に貢献
地球温暖化や酸性雨などの地球環境問題の解決のためには、汚染物質がどこからどのように排出され、どのように物理的化学的に変化し、輸送されているかを明らかにしなければなりません。また地震の被害を低減するには、強い地震動の発生を予測する手法の開発が必要で、さらに地盤の診断から被害を受けやすい地盤を見つけ出し、早めに対策を立てる防災・減災技術が重要になります。このように、人類が地球と共生していくための工学が、ますます必要とされてきています。
(コーディネーター 太田 幸雄)
 大気エアロゾルの気候影響を予測し評価する
大気エアロゾルの気候影響を予測し評価する
環境フィールド工学専攻
大気環境保全工学研究室
教授 太田 幸雄 砕波が取り持つ大気と海洋の親密な関係
砕波が取り持つ大気と海洋の親密な関係
環境フィールド工学専攻
沿岸海洋工学研究室
准教授 渡部 靖憲 土砂災害から命と生活を守る
土砂災害から命と生活を守る
環境循環システム専攻
地盤環境解析学研究室
教授 三浦 清一
 ながれ現象の階層的認識と法則、そして工学
ながれ現象の階層的認識と法則、そして工学
機械宇宙工学専攻
先端流体力学研究室
教授 藤川 重雄 地震動発生のメカニズムを知る強震動予測
地震動発生のメカニズムを知る強震動予測
建築都市空間デザイン専攻
都市防災学研究室
教授 笹谷 努