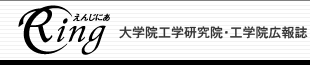卒業生インタビュー
 |
研究開発を通じて社会貢献できる
|
| [PROFILE] 2006年3月 工学研究科 量子エネルギー工学専攻 修士課程修了 ◎出身地/東京都渋谷区 |
|
学生時代の研究を活かして環境技術の分野へ

職場の様子 学生時代はプラズマ計測など、いわゆるプラズマ基礎の分野を研究していました。現在の仕事は、放電・プラズマ技術をコアとした、環境関連機器、放電応用機器の研究開発です。環境技術は自身が強く希望していた分野であり、大学で学習した知識や実験スキルが役立っています。
製品化を目的とした研究開発の難しさも痛感
一方で、コストや特許などの制約から、優れた技術が必ずしも優れた製品に結びつかないなど、製品化を目的とした企業における研究開発の難しさも痛感しています。研究開発に携わる身としては、たとえ狭い分野であっても、世界に通用する専門性を持つことが重要と感じています。
将来は、周囲から信頼されるエンジニアに
ものづくりを本質とする企業においては、当然技術者としての常識を身につける必要があります。高い専門性と、幅広いスキルを着実に習得し、周囲から「あいつに任せておけば大丈夫」と思われるような、そんな信頼されるエンジニアになることが目標です。
 |
「幅広い分野で最先端の技術に触れる仕事がしたい!」そんな想いで知的財産の仕事を選びました。富士フイルム株式会社 |
| [PROFILE] 2002年3月 工学研究科 分子化学専攻 修士課程修了 ◎出身地/富山県富山市 |
|
最先端の技術を知的財産に育てていく仕事

職場の様子 入社して6年間は、知財戦略立案・遂行する業務を担当していました。最先端の技術開発成果を「特許権」という価値ある財産に育てたり、取得した権利を会社の事業のためにどのように使っていけばよいかをコンサルトする業務です。
モノ作りからビジネス展開まで幅広く担当
今はさらに仕事の幅が広がって、知的財産に関する契約、ライセンス交渉、紛争解決の業務を担当し、事業活動をサポートしています。最前線にいる技術者や営業担当者と一緒に、モノ作りからビジネス展開までかかわっていけるところ、それがこの仕事の面白さです。
法律と技術に精通したプロフェッショナルへ
取り扱う技術分野はさまざまですが、これらの技術を理解し、契約・交渉・戦略立案業務を進めていく上で、学部や大学院で培った「技術者魂」が役に立っています。10年後は、法律の知識やスキルを磨き、技術者としての経験を生かしてグローバルな技術経営を主導できる仕事をしていたいです。
 |
国境を越えたグローバル化の進展。
|
| [PROFILE] 1995年3月 工学部土木工学科卒業 2004年12月 博士(工学) ◎出身地/北海道小樽市 |
|
海の仕事がしたくて、港と海の研究の道へ

職場の様子 港町小樽の生まれで、毎日汽笛を聞きながら、漠然と海の仕事がしたいと思っていました。迷わず港と海の研究の道へ進み、海岸侵食の研究に取り組みました。実際に海の深さを測ったり、古い地図を眺めたり。海岸工学を学びながら、海を身近に感じた貴重な体験でした。
日本の活力を支える港湾の政策や計画立案を担当
国家公務員になったのも、港の根本となる政策的な仕事がしたかったから。貿易立国の日本で、輸出入貨物の99.7%を取り扱う港湾は、わが国の活力を支える重要なインフラです。世界各国とのつながりの中、産業の動向を把握しながら、港湾の政策や計画の立案を担当しました。
グローバルな思考で、地域のための仕事を
世界各国の港湾プロジェクトに参画する機会にも恵まれました。北海道の漁港計画では、各地の漁業者の方々と触れ合いながら、日本を支えているのは地域の人々だと実感。10年後の世界の中の日本を見据えたグローバルな思考で、地域のための仕事ができるよう自分を磨ければと思っています。
 |
いつのまにか研究が面白くなった10年。
|
| [PROFILE] 1997年3月 工学研究科 土木工学専攻 博士後期課程修了 ◎出身地/北海道 |
|
先が見えずに苦労を重ねた大学院時代

研究の様子 私の大学院時代は「厳しかった」の一言です。研究のゴールが見えないまま、一人で闇雲に文献を調べ続けるものの、良く理解できずに失敗を繰り返す毎日。博士後期課程の3年間でトライしたことの大半は成果に結び付かず、常に時間に追われていた苦しい思い出が強く残っています。
10年経って実を結んだ、あの頃の苦労
それから10年後の今、学生時代に全くものにならず、当時は諦めていた研究を、欧州の大学との共同研究やプロジェクトの中で進めています。昔、何度もつまずき理解できなかった事が経験を重ねるうちになぜか分かるようになり、今となっては欠かせない私の力になっています。
10年後も、今の自分が信じる研究者の道を
新たな真実を見つける研究と、それを学生に伝える教育、その本当の面白さを知ることができたのも、大学院での貴重な経験があったからこそ。10年後も、今と同様に学生たちや卒業生たちと一喜一憂しながら、今の自分が信じる研究者としての道を歩いていたいと思います。