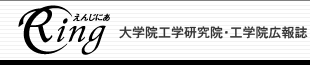Four Lives 04
 |
環境循環システム専攻 |
[PROFILE] |
|
研究編
信頼される
技術者を目指して

職場の様子 私は、1996年に北海道工業大学を卒業後、北海道開発局に就職し、現在の職場(寒地土木研究所)で13年間、スケーリングに関する実験・調査に従事してきました。厳しい財政事情の下で構造物を維持管理することは大変難しく、現場からも多くの技術相談を受けるようになりました。そういう環境の中で、質の高い意見が述べられるよう、高度な専門知識を身につけ、信頼される技術者に成長したいという意識が芽生え、社会人として大学院博士後期課程に入学することを決意しました。
現在私は、コンクリートのスケーリング劣化の挙動解析を行っています。北海道のような寒冷地に建設される土木コンクリート構造物は冬期間、凍結と融解の繰り返し作用を受けます。コンクリートに水分が多く含まれている場合、水の凍結による膨張圧で、コンクリートは損傷を受けます。一方、海水が飛来する沿岸部や、道路に凍結防止剤が撒かれる地域の融雪水には塩化物イオンが含まれており、これがコンクリートに供給されると、水の凍結膨張挙動が活発化し、コンクリートがうろこ状に剥げ落ちるスケーリング(図1)が急速に激しく進行します。スケーリングは、コンクリート断面の欠損や鉄筋腐食の促進が危惧される劣化ですが、劣化のメカニズムは十分解明されておらず、スケーリングの進行性を予測・照査する設計法もまだ確立されておりません。その設計法を確立・提案することが私の研究目的です。

職場の様子

図1 スケーリングによる鉄筋の露出・腐食
(北海道内の山間部の橋梁)
生活編
e-learningの
有効活用
勤務先の寒地土木研究所では、スケーリングに関する研究以外にも数本の研究テーマを受け持っています。さらには、日常の積算・監督業務、関係機関との協議・説明資料の作成、打ち合わせや技術相談、研究委員会活動の対応も行っており、知らぬ間に予定がスケジュール表に書き込まれることも、しばしばです。勤務先では慌ただしい日々を送っていますが、研究データの整理と博士論文の執筆は、空き時間ができればいつでも取り組めますので、不自由さは感じていません。また、博士後期課程の修了には当然、単位の修得が必要です。「日常の勤務を続けながら毎週、定刻の講義に出席できるだろうか…」と入学前に悩んだ時期もありましたが、インターネットを通じて自分のペースに合わせて受講できるe-learningシステム(図2)のおかげで、仕事と大学院生活の両立を図ることができています。環境面では十分な配慮をいただき、大学には感謝しています。あとは、自分のやる気と頑張りだけです。ご指導いただいている先生方、大学院入学にご理解いただいた勤務先の方々、そして家族の期待に応えるために!

図2 e-learningの画面
 Four Lives01
Four Lives01
エネルギー環境システム専攻
応用熱工学研究室
修士課程2年
長沼 伸司 Four Lives03
Four Lives03
応用物理学専攻
生物物理工学研究室
博士後期課程3年
伊東 大輔
 Four Lives02
Four Lives02
環境創生工学専攻
サニテーション工学研究室
修士課程2年
二宮 暢子 Four Lives04
Four Lives04
環境循環システム専攻
資源システム工学研究室
博士後期課程1年
遠藤 裕丈