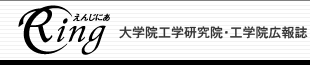卒業生コラム
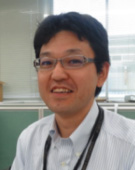 |
一歩先行く
|
||||||||
[PROFILE]
|
|||||||||
あの日を境にして
2011年3月11日。 読者の多くもこの日を忘れることはないと思いますが、原子力に携わるものとして決して忘れてはならない日です。 福島第一原子力発電所の事故以来、以前に増して原子力発電の是非が問われています。 社会からの信頼を毀損してしまった原子力安全ですが、我々原子力エンジニアとしては、眼前の課題に真摯に向き合い、少しでも安全性の高い原子力技術を提供することが使命です。
原子力って難しい……?
原子力という言葉を聞くと「難しい」「怖い」という印象を持っている方が多いのではないかと思います。
大学で原子力工学を専攻する以前は、私も同じでした。
原子力産業は、原子炉工学、放射線工学といった原子力特有の分野から、流体力学、熱力学、電磁気学、材料力学、土木・建築工学、計算科学というように、思い当たるだけでも非常に幅広い分野の融合で確立していると言えます。
私は学生時代に原子炉工学を専攻し、種々ある原子炉タイプの中でも沸騰水型原子炉(BWR)の安全性に係る研究を行いました。
扱う分野は多少違いますが、現在もその延長線上で安全研究を続けています。
原子力が対象とする幅広い分野の中で、関わりの深いものとそうでないものがありますが、目指すところは「一歩先行く原子力安全」。
この目的のためには、少し距離があって知識の浅い分野であっても意欲的に挑戦しなければなりません。
もちろん、私たちは一人ではありません。
効率的に社会に原子力安全を提供するためには、やはり効率的に技術革新を行う必要があり、良好なチームワークとそのためのコミュニケーションが欠かせません。
 ▲原子炉用燃料集合体の性能確認試験の準備作業の様子。
▲原子炉用燃料集合体の性能確認試験の準備作業の様子。
燃料の安全性評価のための重要な試験ですので、丁寧な作業が求められます。
巨人の肩の上に立つ
 ▲大規模な試験は海外で実施することも。
▲大規模な試験は海外で実施することも。
現地のエンジニアとの交流もとても大切です。
原子力の安全性は、実物を使って確認することは容易ではないので、シミュレーションも駆使して確認することが多いです。
チェルノブイリ原発、福島第一原発の事故のように、ひとたび事故が起きると生命や環境への影響が著しいため、どのようにシミュレーションするかがとても重要です。
偉大な先人たちは、工夫を凝らしてシミュレーションを構築し実行してきました。
こういった過去の遺産を継承しつつも、新しい技術の進展によって得られたデータを分析し、有用な知見を掘り出して、原子力安全に役立つ新しい方法を開発することも私の仕事のひとつです。
研究では、真新しさも重要ですが、裏返してみれば、それも過去の知見を礎としているものです。
先人が築いてくれた基礎に小石を積み上げる感覚で開発を進めています。
人生の滑走路
お金は無いけど時間はある……私も大学生のころに良く言われました。 学生時代は刺激も多く、社会に出る直前の多感な時期のため、その後の人生に大きな影響を与えます。 確かに使える時間は多く、この時間をどのように使うかはもちろん自由ですが、課外活動なども含めて、ここで得た経験は一生ものだと思います。 長い人生から見ればとても短い学生生活ですが、実り多いものにして欲しいと思います。 時には遊ぶことも忘れずに。