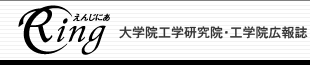卒業生コラム
 |
潤滑油の奥深さを実感しながら
|
||||||||||
[PROFILE]
|
|||||||||||
就活中に出会った
「ものづくり」観
「ものづくり」に興味があり、大学院入学をきっかけに理学部から工学部に転入しました。潤滑油との出会いは、メーカーを中心に就職活動を進めていた時に、ふと「ものづくりを支えているものは何だろう?」と考えたことがきっかけでした。製品は主に機械が作りますが、その機械の性能を保つためには潤滑油が必要です。摩擦の低減・金属の防錆といった機械の作動及びメンテナンスを行う役割を持つ潤滑油は「機械の血液」と呼ばれ、ものづくりの中でも重要な分野です。専攻である有機化学の知識も手伝ってこの仕事を選択しました。今では、自分たちが「ものづくりを支えているんだ!」という気分になります。たまにですが(笑)。
身近で高性能な潤滑油って?
 ▲実験の様子。初め自分の手でゴムを試作し、何回も伸び縮みさせました。
潤滑油のもっとも身近な例はエンジンオイルです。近年、自動車の低燃費化が謳われていますが、それにはエンジンオイルも一役買っています。「機械の血液」である潤滑油の中でも、エンジンオイルは「高性能な血液」です。何よりもまず「長寿命=劣化しにくい」必要があります。また、油は低温ではドロリとした粘り気があり、温めるとサラサラしてきますよね? エンジンオイルは北海道でも沖縄でも使われるので、温度変化に強くなければなりません。潤滑油としての性能を持ちつつ、さらに「どの環境でも一定のスペックを発揮し、かつ長寿命である」という+αが低燃費オイルの必要条件なのです。常に進化している車の技術に合わせて、エンジンオイルも進化するべく研究開発が昼夜行われています。
▲実験の様子。初め自分の手でゴムを試作し、何回も伸び縮みさせました。
潤滑油のもっとも身近な例はエンジンオイルです。近年、自動車の低燃費化が謳われていますが、それにはエンジンオイルも一役買っています。「機械の血液」である潤滑油の中でも、エンジンオイルは「高性能な血液」です。何よりもまず「長寿命=劣化しにくい」必要があります。また、油は低温ではドロリとした粘り気があり、温めるとサラサラしてきますよね? エンジンオイルは北海道でも沖縄でも使われるので、温度変化に強くなければなりません。潤滑油としての性能を持ちつつ、さらに「どの環境でも一定のスペックを発揮し、かつ長寿命である」という+αが低燃費オイルの必要条件なのです。常に進化している車の技術に合わせて、エンジンオイルも進化するべく研究開発が昼夜行われています。
潤滑油の意外な分野に挑戦
昨年の12月、私は原料油の担当になりました。車や機械の潤滑油を担当すると思っていただけに少し驚きました。タイヤなどのゴムの原材料として使用する潤滑油を原料油と呼びます。意外かもしれませんが、ゴムの原料には潤滑油が数十%添加されており、これがゴム中の粒子間の流動性を増やす機能を果たします。ゴムの種類や用途によって使う潤滑油も様々なので、需要家が抱える問題も多様です。これらの問題に対して、現場で何がどのように問題となっているか、現状をしっかり把握することを心がけながら解決に取り組んでいます。とは言えまだまだ知識や経験が足りないので、同期や先輩の力を借りながら、需要家の期待以上の答えを出すべく、勉強の日々を送っています。
遊びも学びも思う存分に!
北大にはたくさんの研究室があり、最先端の研究をいろいろと見聞できます。他大学から来た私にとって、非常にうらやましい環境でした。北海道という恵まれた大地で遊ぶことも大事ですが、北大の素晴らしい環境を活用して、ぜひ興味のある分野を見つけて挑戦してください。北海道で得た経験(遊びも学びも!)は決して無駄にはならないはずです。学生である時間を大切に、思う存分楽しんでください。 ▲更油作業の様子。実際の潤滑油の使用環境・問題点を勉強できる貴重な機会です。
▲更油作業の様子。実際の潤滑油の使用環境・問題点を勉強できる貴重な機会です。