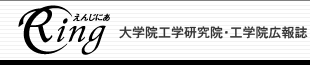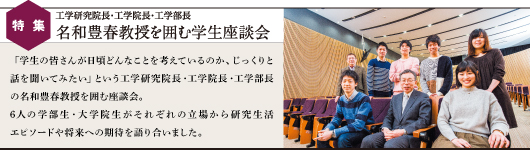心に残る一冊は
何度読み返しても面白い
司会 眞下君から質問が出ています。「おすすめの本を教えてください」。
眞下 僕自身は子どもの頃に読んだ『星の王子さま』が好きで、大学に入ってから英訳テキストを引用した授業があり、あらためて読み返してみました。大人にも訴えかけてくる本質的な内容が深く心に残っています。
名和 良い読書体験ですね。私のおすすめ本は、司馬遼太郎の長編歴史小説『坂の上の雲』です。明治を舞台にした秋山好古・真之兄弟と正岡子規たちの活躍を夢中になって読みふけりました。良い本というのは何度読んでも面白く、読むたびに共感するところが変わります。若い頃は秋山兄弟の快進撃に心が躍りましたが、だんだん自分も年を重ねていくと大山巌などのリーダー像に自然と目が行くようになりました。
よかったら、司会の髙井先生もおすすめ本を教えてくれませんか。
司会 私は評論家の加藤周一が書いた『羊の歌』をおすすめします。多様性を身につけながら生きてきた著者の生き方に感銘を受け、高校でも大学でも、そして先ほどの名和先生のお話のように今でも読み返しています。学生の皆さんからも一冊、聞きたいですね。
鈴木 僕は最近読んだ本の中で、『七帝柔道記』が面白かったです。著者の増田俊也さんは北大の柔道部出身。自身の体験も交えて北大柔道部員たちを描いた青春群像小説でした。自分も学部時代は軟式庭球部に入っていたので、皆でひとつの目標に向かって頑張る姿に素直に共感できました。
司会 では次に大学院生の皆さん、大学院進学の動機を聞かせてください。
古川 正直に打ち明けますと、私は学部時代は微分積分などの数学が苦手で、課題提出にもかなり苦労したほうでした。ですから所属する研究室を選ぶときに、生物物理工学研究室の存在を知り、「同じ工学でも、興味のある生物や細胞に関する研究をできるところがある!」とわかり、とても嬉しかったです。実際に研究を始めたらどんどん面白くなってきて、もっと知りたいという思いが募って大学院進学を決めました。今の研究室に出会えてなかったら学部で卒業していたと思います。
名和 とても良いお話ですね。研究者に必要なものは今、古川さんが「どんどん面白くなってきた」と話してくれたようなワクワクする気持ちです。北大生は誰もが学問的な素地を持っています。あとは、いかにワクワクできる題材を自分で探せるか。楽しさこそ、研究を続ける原動力になります。
鈴木 僕はもともと建築デザインに興味があり、工学部に入ってから建築物の構造や環境について詳しく学びたくなり、建築環境学研究室に決めました。工学部に進んだ時点で大学院進学はごく自然な選択肢でした。将来就職しても、公共施設などの室内環境の改善に関わるような研究を続けたいです。
山崎 僕は東日本大震災をきっかけに、環境やエネルギー問題に貢献する工学研究に関わりたくて、原子力環境材料学研究室に決めました。今やっている土壌中のセシウムに関する研究も、社会へのフィードバックが期待できる内容なので、やりがいを感じています。早く社会に出たいので修士課程修了後は就職希望ですが、どの分野の企業に入っても社会的な課題にどうアプローチしていくか、という考え方は活かせるのではないかなと思っています。
修士論文の執筆は
理想的なアクティブラーニング
司会 次の質問に移りましょう。「就職活動中の学生にアドバイスをお願いします」。
名和 まず思い浮かぶのは、マニュアル本に頼りきってしまう危険性に気づいてほしいということです。というのも民間企業にいた頃、私自身が採用面接を担当していたので、決まりきったQ&Aはもう十分。紋切り型のやりとりを終えたあとに「じゃあ、予行演習はおしまいです。これから本番の面接を始めましょう」と言って学生を驚かせたこともありました。
私よりさらに上を行く上司もいました。学生が「英語が得意です」とアピールすると、不意に新聞のTIMESを渡して「何ページを5分間読んでください。書いてあることについて質問します」と言う。学生は青ざめます。でもそれは英語力を見たいわけではなく、突発的なことに対して機転がきく人材かどうかを知りたくてやったこと。脱マニュアルのところで見えてくる本人の資質を、企業の面接官は見たがっています。
では、私の研究室で実際に学生たちにどう指導しているかというと、「修士論文をしっかり書くこと」を繰り返し伝えています。何が問題で、どう解決していけばいいかを論理的にわかりやすく説明する修士論文の執筆は、まさに理想的なアクティブラーニング。各企業の人事担当者からも「非常に実践的な指導をされていますね」と高く評価していただいています。
川﨑 僕のイメージでは、企業には営業のプロがいるので、技術者がお客様のところに行って説明するという場面があまり想像できないのですが、やはり技術者にも「わかりやすく説明する力」は求められますか?
名和 企業や研究所で新製品をつくる場合、その製品を一番理解している人物は、つくった本人である技術者です。製品の特徴をわかりやすく説明する、あるいはユーザーが気にかけている問題点を素早く見つけ、それを解決できるように修正する。それは技術者だからできること。
ものづくりにおいて、最初に試作したプロトタイプがそのまま実社会で役に立つというケースは非常に稀であり、基本は次々と明らかになる問題点を解決していきながら次の試作に活かしていくケースがほとんどです。それは指導教員に修士論文を持って行って、修正点を指摘されて直していくプロセスとまったく同じこと。その意味でも修士論文をしっかり書く経験が重要になってきます。
それともうひとつ、元面接担当として本音を申し上げるならば、同じような成績の2人で迷った場合、目が行くのはやはり明るい人。その場を明るくしてくれそうな面白さを持っている人に魅力を感じます。その面白さは勉強だけで培えるものではなく、先ほど話した読書体験や部活、趣味でも何でもいい、多様性のある学生生活で自分を磨いている人には、自然と「一緒に働いてみたいな」という気持ちがわいてきます。
眞下君は博士後期課程の進学を希望しているそうですね。
眞下 はい、先輩や先生から世界に通じる研究者になるには博士後期課程修了が大前提だという話を聞いて、自分も続きたいと思っています。
名和 先輩たちの言うとおりです。博士号を持つ技術者はそのまま経営者になるケースも多く、就職の際にも企業は、博士後期課程修了者を十分な戦力になってくれる人材として注目しています。頑張ってください。
司会 ものづくりにおいて、北海道大学は産学連携にも積極的に取り組んでいます。
名和 産業界と組む産学連携は、学生にとって最先端の技術開発に参加できる貴重なチャンスです。ドイツのミュンヘン工科大学を例にあげると、大学内に産学連携専用の施設があり、今非常に重要視されている機密漏洩対策のセキュリティも万全です。我々日本の大学もこれから海外のレベルに追いついていくべきであると考えています。
企業が時間も人材もかけられないような基礎研究など、大学ができることはたくさんあります。先生たちにもぜひ産学連携に着目していただき、学生たちの成長の場を広げていってほしいと考えています。私がよくやるのは、学生と企業が直接話せる状況をつくること。自分はさりげなくその場を外れて、学生に企業の生の声を聞かせています。特に若手の社員の方には、学生も緊張せずに制作秘話や企業の本音を聞き出すことができるかもしれません。こうした産学連携の体験がある学生は、就職活動に入っても志望動機を明確に言える人が多い。体験に裏打ちされた目標を見つけやすくなるのだと思います。
鈴木 僕も現在、企業と共同研究を進めているので、名和先生のおっしゃっていることがとてもよくわかります。自分の研究が社会に役立つ実感を持てるようになりました。

▲ 名和工学研究院長は民間企業時代、採用面接を担当したこともあり、リアルな面接エピソードを明かしてくれた。