特集 04
北海道、日本と共に世界へ To the world with Hokkaido, Japan!!
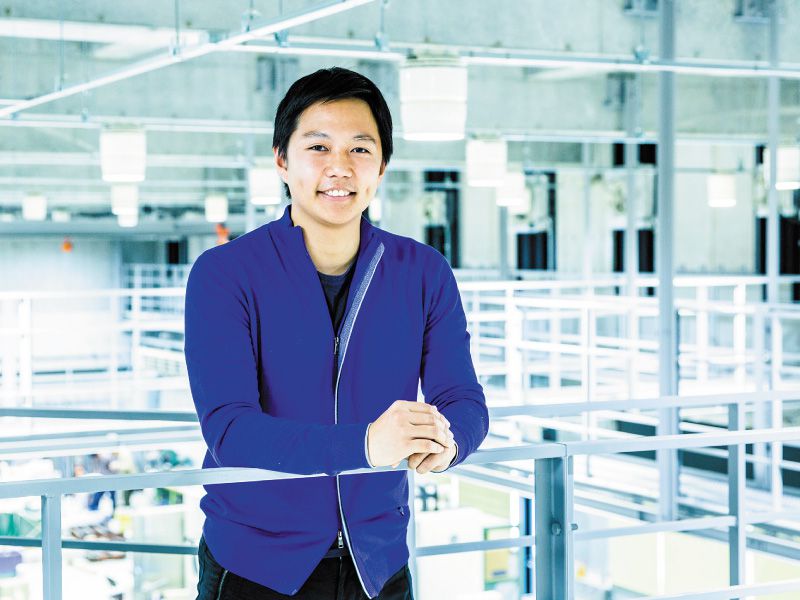
いろいろな価値観に触れながら
目指すは世界に通じる研究者に
環境フィールド工学専攻 河川流域工学研究室 博士後期課程2年
岡地 寛季
国際的な場面で議論する力
世界最高峰の議論場を体感
私の所属する河川流域工学研究室では、河川の氾濫や積雪のメカニズム、火星の地形の形成メカニズムなど幅広い分野をテーマとしています。その中で私は台風などの強風時に海面付近で大気と雨、砕波飛沫によって形成される混相流がどういったふるまいをするのかを実験や観測、理論解析から明らかにし、台風への影響を定量的に評価する研究をしています。自然相手の複雑な物理現象を解明することが防災・減災に繋がり、さらには将来の変動する気候に対する適応策の策定に繋がると考えています。
こうした研究は海外でも盛んに行われており、私も学会や会議など様々な場面で議論を交わしてきました。その際に必要となる英語力や本質的な議論をする力は、国際的人材育成プログラムの「English Engineering Education(e3)」と「北海道大学大学院特別教育プログラム新渡戸スクール基礎プログラム」で養うことができました。
昨年度はイギリスで開催された地球環境流体力学サマースクールに参加し、これまで培ってきた力を使って様々な議論を行いました。休日にはケム川でパンティング(図1)をしたり、バーに飲みに行ったりと有意義な時間を過ごしました。サマースクールは研究の議論にとどまらず、世界情勢やそれに対して学生である自分たちに何が出来るのかを真剣に話しあう場でもありました。意見を言わなければ眼も見てくれない厳しい空間で、学内の議論では感じられない異なる雰囲気を実感しました。この体験はさらなる高みを目指すきっかけとなりました。

全国・道内の「若手の会」
深い議論でより高みへ
国内でも学会では学びや新たな出会いがあります。私は全国規模で展開している「若手の会」メンバーとして勉強会や現場見学会(図2)、懇親会を企画しています。議論の場が増えれば増えるほど次の学会に向けてより研究を進めて深い議論をしたいという気持ちになり、この分野の将来を担う我々が意欲的に研究に取り組むきっかけになります。道内でも新たに「若手の会」を立ち上げ、大学や分野を超えた横のつながりを築こうとしています。こうした積極的な議論を通じて世界に通用する研究者になることを目指して、日々研究しています。
