特集 01
九大に通う北大生? Student belonging to two Universities
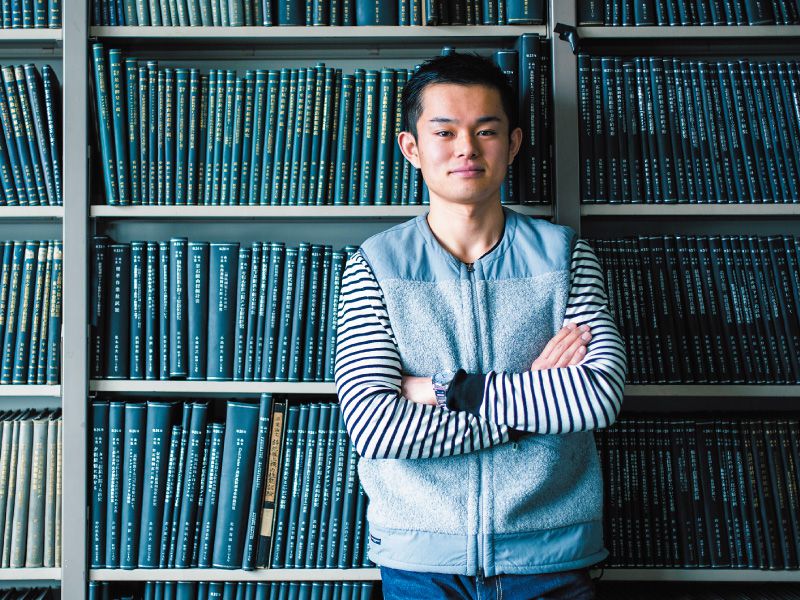
ものおじすることなく
自分から動く精神を鍛えてもらいました
共同資源工学専攻 環境地質学研究室 2019年3月 大学院工学院共同資源工学専攻修了
山本 幹
九州大学の学生として過ごした
刺激的な2カ月間
外の世界と触れ合うことが好きだった私は「将来は海外で活躍したい」と思い、海外調査ができる資源循環システムコースに進学しました。学部では、コースの長期インターンシップでフィリピンや韓国に赴き、現地の学生と一緒に研究や調査に取り組みました。現在所属する研究室では、海底熱水鉱床と呼ばれる鉱床から採取された鉱石中に含まれる高溶解性物質の溶け方や形成過程を調べる研究をしています。
学部4年次の専門研究だけでは時間が足りないと感じて進学を決めた大学院では、新設の「共同資源工学専攻」を選びました。本専攻は北大と九大の共同教育課程で、資源系教育のほか、資源産出国とのつながりを作るため留学生を交えた英語による授業が行われるなど、とても挑戦的な環境が整っています。
九大での2カ月間の学生交換プログラム中は寮で暮らし、1日中授業を受け、空いた時間で研究に取り組みました。資源研究の中でも北大では受けられない授業を履修し、異分野の研究に取り組む先生や学生と議論ができた刺激的な時間でした。生まれて初めて訪れた九州でグルメや観光など地元の文化を体験するという意味でも、視野が一気に広がった2カ月間になりました。

日本では体験できない
現役鉱山でのインターンシップ
共同資源工学専攻では、海外インターンシップへの参加が必修科目です。修士1年次の渡航先は、南アフリカ共和国のプラチナ鉱山を選びました。この鉱山の開発には現地の資源開発会社のほか、日本の大手商社やプラント会社も参画しています。日本の鉱山のほとんどが閉山したなか、現役で稼働中の鉱山を訪れた時の感動は忘れることができません。また、現地の技術者や遠く離れた現場で働く日本人との交流は、就職活動を控えていた当時の私にとってその後の人生を考えるうえで貴重な経験となりました。
九州、アフリカという慣れない環境で戸惑うことも多々ありましたが、本専攻でしか経験できないことを通して、目標を定めたら自分から積極的に動き出す精神を鍛えられたように感じています。
