特集 02
川や水処理施設の水質を多角的に分析する Water quality analysis in rivers and water treatment facilities
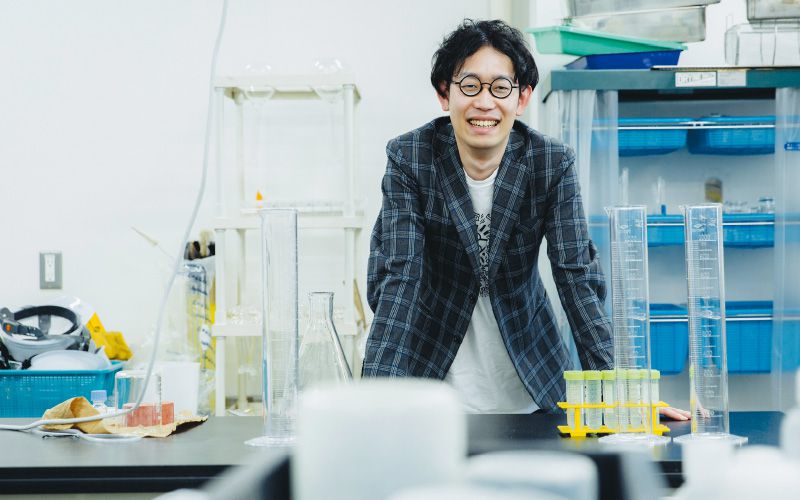
持続可能な都市生活を支える水代謝システムの確立を目指して
環境工学部門 水環境保全工学研究室 助教
中屋 佑紀
化学と生物学の視点で水代謝システムの出口を追跡
水環境に関する研究の中でも下水処理のような“出口”のプロセスにはあまり光が当たりませんが、実はこの下水処理の効率を高めることが、持続可能な都市づくりや私たちの衛生的な都市生活を大きく下支えしています。生物が栄養を摂取して排出する「代謝」のように、滞りのない水代謝システムを維持するには、水源だけでなく下水処理水の放流先である河川や湖、海の水環境や、水処理施設の状態を正確に把握・監視することが重要です(図1・2)。
私は長年自然界に存在する腐植物質の数百年単位の発生と消滅のメカニズムを調べるため、有機化学的指標の追跡に取り組んできましたが、2021年度に着任した当研究室がもともと得意としていた微生物やウイルスを分析する生物学的指標や、重金属を対象とする無機化学的指標と組み合わせることで、より多角的な分析が可能になりました。現在は河川や水処理施設の水質を、数日単位の時間スケールで追跡しています。


顔認証の技術も活用する欲張りな研究が楽しい!
下水処理において、下水中に存在する微生物の塊を「活性汚泥」と言います。活性汚泥の表面は微生物が作り出した糊のような役割をする有機物で覆われており、私はその有機物が下水中の汚濁物質を捕らえて、水をきれいにするはたらきに着目しています。最近では、微生物や有機物のはたらきに着目した研究を北大農学部にあるバイオガスプラントにも適用し、牛糞尿由来の微生物によってさらに効率よく燃料ガスを取り出すことができるのではないかという研究も始めています。
さらにユニークな特徴として当研究室は、人間の知覚では見分けられない活性汚泥の画像に、顔認証などで利用されているディープラーニングの技術を活用することで、汚泥の処理能力を予測する技術の開発にも取り組んでいます。活性汚泥の“顔”を見るというような情報工学の領域にもまたがる欲張りな研究にはトライ&エラーがつきものですが、様々な技術を組み合わせたりつなげたりして、これまでにない新たなデータを目の当たりにするのが楽しみです。
Technical
term
- 活性汚泥
- 好気性の細菌類や原生動物などの微生物、有機性および無機性物質の集まり。下水中の汚れを分解し、水を浄化する役割を果たす。