巻頭特集
インフラテクノロジー開発拠点 土木工学研究棟を探検!
土木工学研究棟の設計コンセプト
7月、最新鋭の研究設備と快適な研究環境を備える土木工学研究棟が竣工しました。これまでの土木工学研究は、高度経済成長期における多様なインフラ整備を推し進めるため、コンクリート工学、橋梁工学、河川工学、土質工学など建設対象物別の独立した研究室体制において行われてきました。一方、気候変動下で激化が予想される自然災害、将来のサステナブル社会に向けて不可欠なエネルギーシフト、人口減少、少子高齢化に伴う日本の現在及び将来の社会問題に対して、従来の枠組みを大きく超えた問題解決型の研究体制が必要です。
新研究棟は、従来の研究室体制から脱却し、現在及び将来生じる社会問題解決へ向けた研究枠組みの形成に柔軟に対応できるよう、次のコンセプトの下に設計されました。
- トップレベルの研究環境
- 研究組織に依存しない機能別空間設計
- 多用途・多目的利用を可能とする高効率空間機能
- 広報・アウトリーチ機能の充実
これらの設計コンセプトに基づいた先端研究設備と研究空間を紹介します。
大水槽群が立ち並ぶ大実験室
1階地球流体実験室(写真1)には、研究棟の両端の壁までを打ち抜くオープンスペースの中に、長さ20mにも及ぶ海洋波浪や河川の流れを再現する大水槽群が立ち並び、海岸災害、洪水の再現や防災施設に係る先端研究が行われます。
2階廊下及びキャットウォークからは、実験の見学等を行うことができ、広報や研究アウトリーチに利用可能です。

寒冷地研究の先端実験環境
凍結融解下の建設材料性能評価、永久凍土内の構造物の応答、冬季の堤防性能評価など、世界をリードする北大の寒冷地研究を支援する構造工学実験室(写真2)、低温構造試験室、恒温土質試験室、さらには地球温暖化による偏西風や熱輸送形態の変化を模擬する水循環恒温室など、先端研究環境が整備されています。

機能別研究スペース
従来の研究室体制の空間設計を見直し、Student Room(問題解決型プロジェクトごとの広い空間)で大学院生、学部4年生が研究します(写真3)。
Student Roomはデスクワークに特化した研究スペースであり、休憩、飲食は2〜4階に設置されたリフレッシュラウンジ(写真4)で、ミーティングやゼミは共同利用が可能なセミナー室(写真5)、各種イベントは廣井勇記念室(写真6)、というように、空間機能を分けて快適に研究活動を行うことができるよう、設計されています。
-

写真3 170名もの学生が研究を行うStudent Room -

写真4 2〜4階に配置されたリフレッシュラウンジで息抜き -
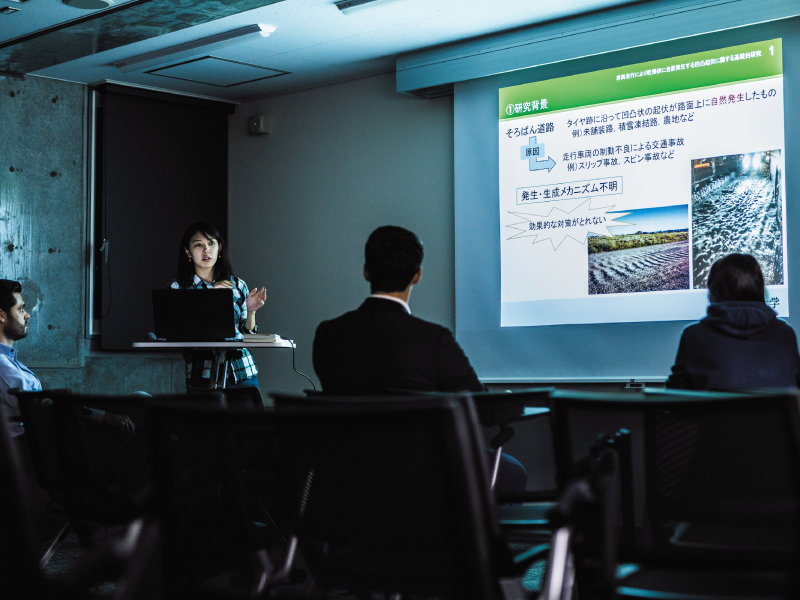
写真5 音響映像システム完備のセミナー室
ひろ~い多目的・多用途スペース
卒業生からの寄附によって揃えられたモダンな設備をもつ廣井勇記念室(写真6)は、日本の土木工学の父、札幌農学校第2期生の廣井勇博士から、偉大な卒業生の象徴として名を頂きました。
時限付研究者のデスクワーク、学内外の学生、卒業生、教員、技術者の打ち合わせ、作業空間、就職活動やパーティーなど、多用途、多目的に利用可能な空間を提供します。
