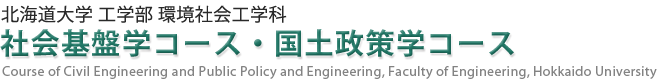FAQ
土木って何?
A1(硬)
大地に公共のための構造物を建設し、新しい環境を造り上げる技術である。この中には、災害を防ぐ治山・治水の工事も含まれる。また、事業を進めるに当たり、多くの関係者の話合いと協調性を必要とするので対人工学とも言われる。
土木技術は、Civil Engineering と言われ私たちの生活や産業の基盤を作り、生活を便利に効率的に、しかも安全・快適にするために環境を造りかえる技術である。
例えば、さきの東北大地震の時には、ライフラインとしての水・ガス・下水・運輸・通信の復旧作業が優先的に行われた。これらの仕事こそまさに土木である。土木は私たちの生活をあらゆる面で支えているといっても過言ではない。将来、さらに様々な災害が日本を襲うかも知れません、その災害に強い街をつくったり、災害から復興するのも土木の仕事です。
A2(軟)
みなさんが仕事やデートで街を歩くとき、山や海でレジャーを楽しむとき、目に映る風景にも土木はあるのです。かわいいレンガの小道、きれいな橋や迫力のダム、港に鉄道や空港も土木によって創造されているのです。
また、お家でご飯を食べるとき、TVを見て、お風呂に入るときにも、土木は深く関わっています。水道や電気・ガス、通信設備などの整備も土木の役割なのです。
土木は人々の生活に密着しているため、欧米では土木の学問である土木工学をCivil Engineering(市民や社会のための学問)と呼んでいます。
土木は、人にとって安全で快適な環境を考え、そのプランを実現するために存在し、人類の歴史と共に進化してきた、土と水を知る環境のプロなのです。
今も、そしてこれからも、人間は地球の住人でありつづけ、そこに生きる多種多様な生命が活きつづけるために、地球にとって良い環境づくりをしていかなければならないと考えます。最近では、バリアフリー・ゴミ処理問題や構造物壁面の植生化、地下空間開発、海洋開発なども土木が取り組んでいます。
また、インフラは、規模、予算やそれが与える影響や効果はいずれも巨大であるため、適切に計画し実行しなければなりません。将来予測、経済状況や周辺環境など複合的な要素を調査、分析して、インフラ整備計画を立てます。こういった政策を提案するのも土木の領域です。
先に述べたようにインフラはすべての面で巨大であり人々と密接にかかわるため、研究領域だけでなく広い視野を持ち全体を俯瞰する力が必要であり、そのような力が身に付きます。事実、卒業生の進路は多岐にわたります。
こんな人の生活と密接に関係し、人の生活を支える領域は他にはありません。人が生活する上で必要不可欠な、やりがいのあることが学べる社会基盤学コース、国土政策学コースへ是非!
就職に関するQ&A
| Q1. | 就職先はどのような所がありますか? |
|---|---|
| Ans. | 技術職としては、公務員、ゼネコン、コンサルタント、電力会社、エンジニアリングなどが多いです。その他には、商社や銀行などに就職する人もいます。 |
| Q2. | 公務員の仕事を教えてください。 |
| Ans. | 社会基盤と国土政策学の先輩は企業だけではなく技術系公務員となる方も多いです。公務員と言っても大きく分けると国家公務員と地方公務員があります。国家公務員は国の省庁に属し、日本の国家としての問題に取り組みます。例えば、東日本大震災の復旧・復興計画をたてることや、このような被害を出さないための防災計画の策定に携わります。地方公務員は、地域に根差し、地域住民の声を反映した地域づくりに取り組めます。 |
| Q3. | 公務員試験の対策は行われていますか? |
| Ans. | 公務員試験の対策は熱心に行われています。先生方が試験対策講義を開いて下さいます。先生方が公表されることのない実際の公務員試験の解答を作って下さり、その解答と過去問の載った黄色本(大学受験の時の赤本のようなものです。)を社会基盤学・国土政策学の2コースの学生は借りることができます。 |
| Q4. | コンサルタントとは何ですか? |
| Ans. | 例えば、橋を造る事業があったとします。コンサルタントとはその橋を建設する為の測量や設計、橋が出来ることによる周辺環境への影響を調査します。 |
| Q5. | ゼネコンとは何ですか? |
| Ans. | ゼネコンとは、実際に構造物を建てる会社のことです。社会基盤学・国土政策学の先輩の多くは簡単に言えば、現場監督のような立場になります。私達は実際に重機を動かしたりせず、工事の工程計画や調節を行います。 |
| Q6. | 就職支援は行われていますか? |
| Ans. | これは、他学科と比べても熱心に行われています。北大の土木は歴史が古く、多くの先輩方が活躍しています。その結果企業からの信頼も厚く、学校推薦枠がある企業もあります。先生方もとても熱心に相談にのって下さいます。社会基盤学・国土政策学の2コース向けの就職説明会も学校で開催されます。 |
| Q7. | どのような事がしたいと思い就職先を選びますか? |
| Ans. | これは人それぞれだと思います。が、私達が土木という世界で活躍しようと思う上で共通する気持ちは、人のため、国のため、世界のために仕事をする!という想いです。社会の為に仕事が出来るのが社会基盤学・国土政策学2コースの魅力です。 |
大学院進学に関するQ&A
維持管理システム工学研究室 D1 三浦泰人
大学院について
| Q1. | 環境フィールド工学専攻と北方圏環境政策工学専攻の違いはなんですか? |
|---|---|
| Ans. | 環境フィールド工学専攻では、河川、海洋、地盤、土、材料といった人々の暮らす環境を対象とし、北方圏環境政策工学専攻では、都市計画、構造、建設材料といった人々が暮らすために必要な社会基盤を対象としています。 |
| Q2. | 環境フィールド工学専攻と北方圏環境政策工学専攻とでわかれているが、つながりはあるのか? |
| Ans. | 二つの専攻を合わせて土木という大きな分野なので、学生間のつながりも先生方のつながりも深いと思います。色々なイベントもあり、同期、先輩、先生方など多くの人と知り合える機会は非常に多いです。 |
| Q3. | 進学率は? |
| Ans. | 大学院への進学率は例年70%程度です。 |
研究室での活動について
| Q1. | 卒業論文や修士論文などで行う研究というのはどういうものでしょうか? |
|---|---|
| Ans. | 土木分野で未解明な現象、新材料を用いた技術開発などの未だ誰も知らないことを解明していくというものです。研究室にもよると思いますが、一人一人に一つの研究が与えられ、それに長い期間をかけて取り組んでいくので、卒業論文や修士論文が完成した時には自分だけの宝物のようなものができた気がするかもしれません。ぜひ、楽しんでください。 |
| Q2. | 先生方とはどのような関わりがありますか? |
| Ans. | 普段、皆さんの授業をされている先生方からマンツーマンで指導して頂けます。その他にも、飲みに連れて行って頂いたり一緒にスポーツをやったりと,かなり身近な存在になると思います。 |
| Q3. | 研究室間のつながりはどうですか? |
| Ans. | 研究内容が近い研究室では、合同でゼミを開いたり、ジンパやスポーツ大会を開催したりしていて、研究室間のつながりはかなり密です。また、土木という大きい枠組みで毎年スポーツ大会を開いて、交流を深めています。 |
| Q4. | 卒業論文or学部、修士論文or修士課程、博士論文or博士後期課程の違いはなんですか? |
| Ans. | 研究に従事する期間が卒業論文:1年、修士論文:2年、学位論文:3年と異なっています。また、専門知識の量や経験値は年々増加するので、大学院に進学すればより深い部分まで追及することができると思います。 |
| Q5. | 他大学との付き合いはありますか? |
| Ans. | 国内外の学会等で色々な知り合いができると思います。また、先生方の紹介で他大学の学生と交流があったりする機会もあります。 |
| Q6. | 国際的な活動はできるのでしょうか? |
| Ans. | 多くの研究室では海外インターンシップや留学を推進しているところもあります。また、自分の研究を論文にして国際会議等で発表することもあるので、世界各地に行くことも多いと思います。留学生も多くいるので、日本にいながら国際的な部分を味わえるかも知れません。 |
| Q7. | お金は大丈夫か? |
| Ans. | 厳しい部分もあります。色々な貸与・給与型の奨学金や授業料の免除申請もあり、それらを申請している学生が大半だと思います。特に、博士後期課程まで進学している人は申請さえすれば学費が免除になるシステムになっています。また、研究助成金や研究者として給料を頂いて研究を行うものもあります。これらは競争率が非常に高いのですが、土木分野で頂いている人も少なからずいます。 |
大学院進学について
| Q1. | 大学院に進学するメリットは? |
|---|---|
| Ans. | 一つは、資格として社会的に認められた修士号、博士号を獲得することができるということだと思います。社会人になってから修士号、博士号を目指すという道もありますが、会社からの援助がない場合の方が多いので、学生としてそのまま進学した方が取得しやすいかと思います。また、各分野の権威の先生方から直接指導して頂いて、じっくりと時間をかけて専門知識・技術を学ぶということは皆さんのこれからの財産になると思います。身に付けられる知識、その時間を共有できる仲間、先輩方、先生方とのつながりはかけがえのないものになると思います。 |
| Q2. | 大学院に進学するデメリットは? |
| Ans. | 収入がないということが一番大きいです。 |
| Q3. | 何が身に付けられる? |
| Ans. | 一つは、専門知識です。色々な人の意見を聞くと、いつ社会に通用する専門知識・技術が得られるかは研究室配属後からだという人が多いです。また、研究室という単位での社会性も挙げられると思います。研究室を会社の構造に例えると、先生という上役、先輩という上司、同学年の同期といった社会ができているので、色々な力が身に付けられると思います。最後に、研究を通じて社会の深い部分を垣間見ることもできると思います。今まで当たり前のように底に存在している土木分野のものが、様々な検討を重ねた結果成り立っているということが研究を通じて見えてくるはずです。 |
イベント・日常生活に関する Q&A
河川研
| Q1. | 部活動・バイトと勉強の両立はできますか? |
|---|---|
| Ans. | 練習の厳しい運動部に所属している先輩が沢山います。両立は可能です。 |
| Q2. | どんな授業がありますか? |
| Ans. | いろいろな科目がありますが、大きなものでは「構造系」「土系」「水系」「計画系」の4つが上げられます。順に、構造物の強度・土や地盤の強度・水の運動の性質、都市計画や国土計画などについて勉強します。詳しくはシラバスを見て下さい。 |
| Q3. | 実験ではどんなことをしますか? |
| Ans. | 構造物・土の強度実験、水路実験、橋梁模型の製作などを行います。自分でコンクリートを作ってみたり、大規模水槽で流体実験を行ったり出来ます。橋梁模型に関しては毎年強度コンテストを開催してグループ間で競い合います。 |
| Q4. | 友達が社会基盤、国土政策コースとバラバラに進路を選択していて、コース分属後にクラスになじめるか心配です。 |
| Ans. | 社会基盤学・国土政策学コースにはグループ学習を盛り込んだ授業(土木工学創成実験・土木計画学演習など)があるため自然に友達が出来ます。また、工学部運動会や綱引きに真剣に取り組むため、友情が深まること間違いなしです。毎年みんななかよしです。 |
| Q5. | 社会基盤学・国土政策学コースならではのイベントを教えて下さい。 |
| Ans. | 大規模インフラの見学ツアーなどを開催します。また、公務員試験対策講座を3年後期から開講します。工学部運動会・綱引き大会の後はもちろん、実習や測量の後に飲み会を開くなど、みんなで和気藹々と楽しく過ごしています。 |
| Q6. | 高校の時に物理を選択していませんでした。今も物理はあまり得意ではありません。 |
| Ans. | 理系一括入試が始まる前も、社会基盤学・国土政策学コースの所属する環境社会工学科では、「化学・生物」、「化学・地学」の学生を募集していました。力学を扱う授業が多いですが、物理が苦手な人でも大丈夫な授業内容になっているので安心して下さい。 |
| Q7. | 女子学生は多いですか? |
| Ans. | 多い年は多いです(笑 |
| Q8. | 社会基盤学・国土政策学コースでの学生生活はどんな感じですか? |
| Ans. | 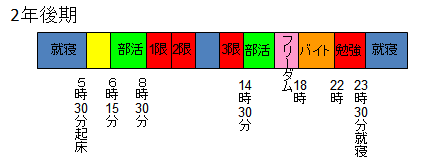
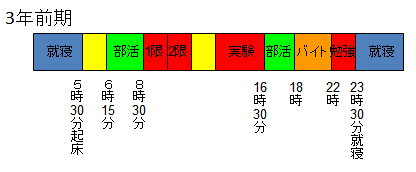
計画的に行動すれば部活もバイトも両立出来ます!! 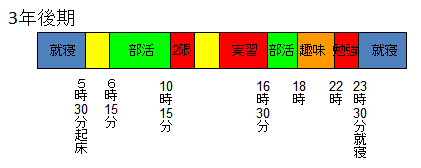
パブリックデザイン演習では都市計画のポスター発表などを行い、グループ学習が頻繁になります。 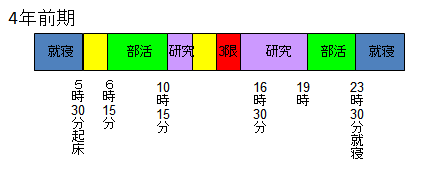
ゼミでの発表や自分だけの実験など、大学ならではの生活が始まります。 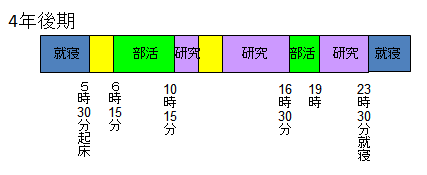
|