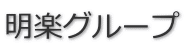研究の進め方
研究のための基礎知識習得から始めて一歩一歩研究を進めています。
はじめての研究分野に踏み出すとき期待とともに不安もあるでしょう。
そのときはぴったりの教科書を探して、
基礎から最前線まで一緒に勉強しましょう。
●卒業論文
卒業論文の最大の目的は、研究とはどのようなものかを知ること、文献の勉強から計算、議論、発表、論文作成までを一通り経験してみることです。したがって、学会で発表できるような成果を出さなければならないという訳ではありません(もちろん結果を出す余裕がある場合は、結果を出して学会で発表するように勧めています)。
テーマの方向付けは、学生と教員が相談して決めますが、4年生は研究を始めたばかりで事情も分からないので教員が勧めるテーマの中から選ぶというのが通常です。ただし、その場合でも、問題設定やモデル設定の詳細はできるだけ学生が考えて自ら選択するという方針をとっています。そのねらいは、独り立ちしたときには自分でテーマを考えて選ばなければならないので、そのためのセンスを早くから高めておくこと、それから自分で決めたテーマを自分で実行するという「自由」と「スリル」と「緊張感」を活用して研究推進力を高めることです。
計算方法は、学生の適性と問題の性格を考えて相談し、理論的手法あるいは計算機シミュレーションあるいは両方、の中から選びます。理論的手法では、方程式を立て解を求める作業を紙の上で行います。積分を数値的に実行したり行列計算をする場合には計算機も用います。一方計算機シミュレーションでは、方程式を数値的に解いて時間発展を求めます。
議論は、毎週1回のゼミで学生が研究の途中経過を発表する際に行います。また、ゼミの前後に個別に1対1で議論します。はじめは、言いたいことがなかなか思うように伝わらなくて苦労しますが、慣れてくると卒論発表会で立派に質疑応答ができるようになります。
●そして、修士論文、博士論文
修士論文や博士論文も、基本的には卒業論文と同じ手順で研究します。ただし、関係する研究分野の事情も分かってくる頃なので、できるだけ自分でテーマを見つけることができるように指導しています。具体的には、教員がいくつかの先行研究の論文を挙げ、学生がそれから1つ選んでゼミで発表し、それをもとにテーマを考えます。もちろん学生と教員が議論してテーマを決めるので、決して困っている学生を放っておくことはしません。また、教員が行っている研究に興味をもった場合は、一緒に研究することも歓迎しています。
博士課程まで合わせて6年間一貫して研究すると、その研究テーマについてエキスパートになれます。
応用物理学専攻では博士課程進学を奨励しています。
博士論文を仕上げるところまで見通しが持てないという人も多いとは思いますが、
そこは「挑戦!やってみよう!」という姿勢でも良いのではないでしょうか。
|