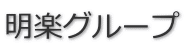スピントロニクス ー電子スピンを操るー (理論)
●スピントロニクス
物性物理工学研究室スピン工学グループでは、
電子のスピンを情報処理に用いるための課題に取り組んでいます。
ご存じのように電子は電荷だけでなくスピンも持っています。
電子が流れる際、電荷とともにスピンを運んでいるわけです。
このスピンと電荷の両方を活用する新しいエレクトロニクスをスピントロニクスといい、
近年活発に研究されています。
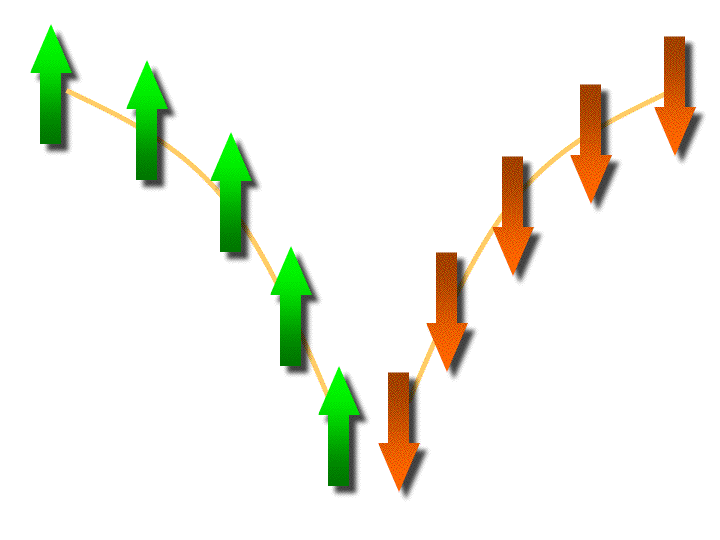
電子のスピン状態には上向きと下向きがあり、これらが1と0に対応し情報を担います。
したがって、まずスピン状態を上向きか下向きに揃えること、
すなわちスピンの偏り(スピン偏極という)を作ることが必要になります。
その上で十分に長い間スピン偏極を維持することも必要です。
われわれは、
(1) 大きいスピン偏極を作る、
(2) スピン偏極の寿命(スピン緩和時間という)を長くする、
という課題に取り組んでいます。
皆さんが、これらの課題を解決することで
スピントロニクスを大きく進展させてくれることを期待しています。
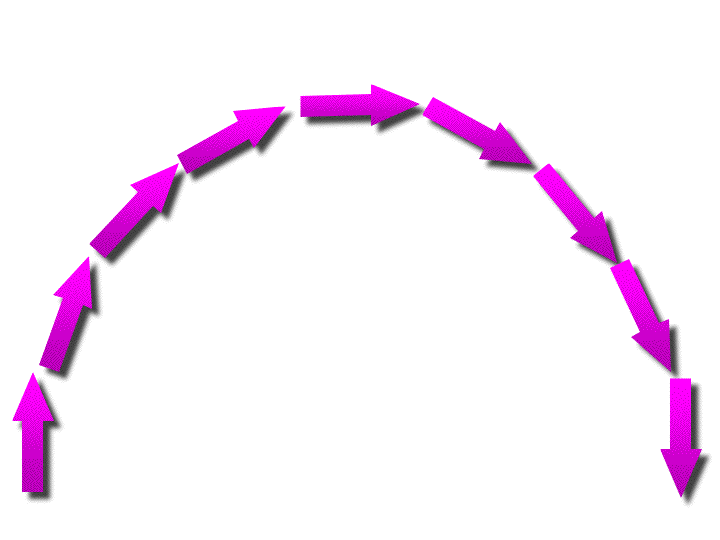
●理論計算
われわれの研究手段は理論計算です。
最適な特性を見つけるために、素子の構想を練りに練った上で、
スピン偏極やスピン緩和時間の計算を素子構造を変えパラメタを変えて繰り返します。
途方もなく多くの条件の中から最適な条件を見つけ出すには、経験と勘が頼りです。
心配しなくて大丈夫です。
地道にいくつも試しているうちに自然と勘が身についてきます。
スピンはミクロな系で量子力学的に振る舞う自由度ですが、
長く親しむうちに違和感なく実感できるようになります。
●スピンホール効果
もう少し詳しくスピン偏極を作る方法を知りたい人のために、
スピン偏極生成方法の代表例であるスピンホール効果について説明しましょう。
スピンホール効果とは、図のように試料に電流を流したとき、
電流の両側の試料端にそれぞれ上向きスピンと下向きスピンが
蓄積する現象です。すなわち試料の両端に反対向きのスピン偏極を生成することができます。
このスピン偏極生成の原動力はスピン軌道相互作用と呼ばれる相対論的効果です。
したがってスピンホール効果は相対論的量子力学に基づく現象です。
21世紀に入ってから盛んに研究されています。
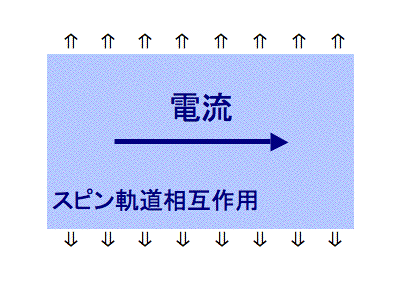
●ホール効果の仲間
皆さんがよく知っている現象にホール効果がありますが、
名前から予想がつくように、上に述べたスピンホール効果はホール効果の仲間に属しています。
ホール効果の仲間を紹介しましょう。
ホール効果とエッティングスハウゼン効果
皆さんご存じのホール効果は、図のように試料のz方向に磁場を加えx方向に電流を流したとき、
y方向の試料端にそれぞれプラスとマイナスの電荷が蓄積しそれが電圧として観測される現象であり、
1879年米国の物理学者エドウィン・ホールが発見しました。
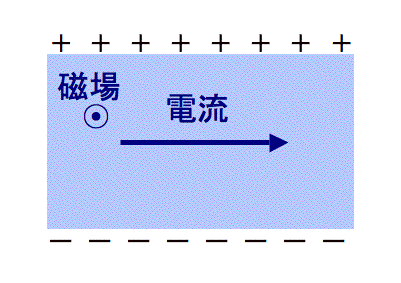
同じ設定でy方向に(電荷の代わりに)温度の勾配が現れるという現象もあります。これはエッティングスハウゼン効果と呼ばれ、 1886年オーストリアの物理学者アルベルト・フォン・エッティングスハウゼンが発見しました。
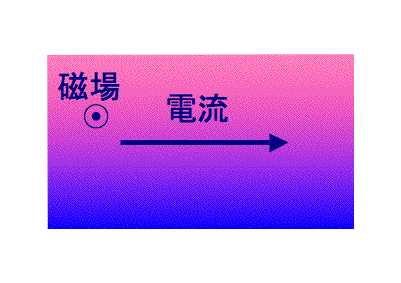
量子ホール効果とスピンホール効果
ホール効果は3次元の電子系で100年以上も前に発見された現象ですが、20世紀後半には半導体ヘテロ接合の界面に形成される2次元電子系に垂直に強い磁場を加えた系(量子ホール系と呼ばれる)において研究が進められ、1980年に量子ホール効果が発見されました。量子ホール効果ではホール抵抗(y方向の電圧をx方向の電流で割った値)が量子化するので、標準抵抗として利用されています。
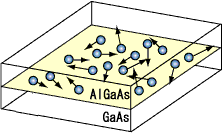 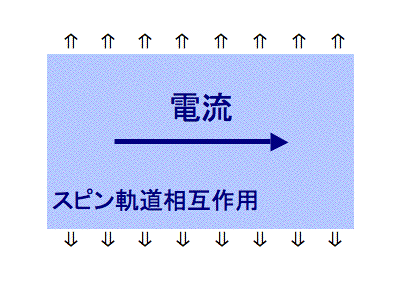
21世紀に入ってから盛んに研究されているスピンホール効果はホール効果とよく似た現象ですが、
その原因は磁場の代わりにスピン軌道相互作用であり、蓄積するのは電荷ではなくスピンです。
この現象はスピン偏極を発生させる手段として有用なので、
スピントロニクスへの応用が期待されているのです。
●電荷・スピン・熱の流れと分布
我々は、電子系における電荷・スピン・熱の流れが磁場やスピン軌道相互作用によって
どのように変貌するのかを明らかにし、
流れがもたらす電位・スピン偏極・温度の空間分布を理論的に解明することに携わっています。
|