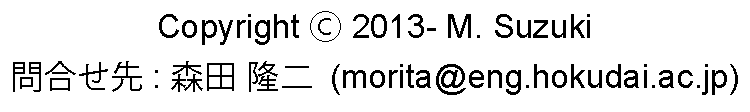(2014/12/12作成開始)
ここでは卒業論文を書くために使うTeX(テフ)の論文の引用の仕方について説明します。
卒論に欠かせない参考文献を便利に管理できるものがBibTeXです。文献番号の管理や参考文献のページを自動で生成してくれます。
BibTeXを利用するためには、まず文献の情報が入ったbibファイルを作る必要があるので、次の項目でそれを説明します。
引用したい参考文献の文献情報が入るbibファイルの作り方にはいくつかの方法があります。bibファイルは通常のテキストエディタ(メモ帳、秀丸、TeraPadなど)やTeXworksで編集可能であるため、手作業で作ります。しかし、論文雑誌では大抵、その論文の情報が入ったbib形式のファイルがダウンロードできるので、それを自分のbibファイルにコピーアンドペーストするだけでよい場合がほとんどです。一部の雑誌や、書籍の場合はbibファイルが用意されていないため、自分で書く必要があります。
まずは、卒論用のbibファイル(ここでは、ファイル名を"bib.bib"とします。)をTeXworksやテキストエディタで作成してください。保存する場所は作成しているTeXファイルが存在するフォルダの中です。
Physical Review Letterなどのアメリカ物理学会の論文誌に載っている論文の引用情報を取得する方法を図1,図2に示します。
Optics LetterやOptics Expressなどのアメリカ光学会の論文誌に載っている論文の引用情報を取得する方法を図3,に示します。ここでは、bibファイルをダウンロードにより引用情報を提供しているため、ダウンロードしたbibファイルを一度テキストエディタで開いて、その内容を自分のbibファイルにコピーする必要があります。
書籍などの場合は自分で自分のbibファイルに情報を書きこまなければなりません。コード1にその書き方の一例を示します。詳しい書き方については、参考文献1を参照してください。
%教科書
@Book{NFO,
author={Govind Agrawal},
title={Nonlinear Fiber Optics, Fourth Edition},
publisher={Academic Press},
address={San Diego, CA},
year={1995}
}
%教科書
@Book{NFOj,
author={Govind Agrawal},
title={非線形ファイバー光学},
note = {小田垣 孝, 山田 興一 訳, (原書: Nonlinear Fiber Optics, Second Edition)},
publisher={吉岡書店},
address={京都},
year={1997},
edition={2nd}
}
%博士論文
@phdthesis{cacao_thesis,
author = {Taro Cacao},
school = {Donuts University},
title = {Topological Charge of Donuts},
year = {2024}
}
%修士論文
@mastersthesis{cacao,
author = {カカお 太郎},
school = {ドーナツ大学大学院レーザー研究科},
title = {ドーナツとトポロジカルチャージの関係性についての一考察},
year = {2021},
}
本文中で引用をするには、引用をしたい場所で\cite{...}コマンドを入れればできます。また、参考文献リストを卒論の最後に作る方法は参考文献を表示するために必要な命令に書いてあります。そして、¥citeを利用して引用した文章をコンパイルするには通常の方法とはコンパイルの方法(回数)が通常とは違うので、コンパイルも確認してください。
参考文献を引用したい場合は、引用したいところで\cite{...}コマンドを入ると引用ができます。...の部分には、bibファイル内で書いた参考文献を表すidを入れる。例えば、bibファイルに
@article{PhysRevA.45.8185,
title = {Orbital angular momentum of light and the transformation of Laguerre-Gaussian laser modes},
author = {Allen, L. and Beijersbergen, M. W. and Spreeuw, R. J. C. and Woerdman, J. P.},
journal = {Phys. Rev. A},
volume = {45},
issue = {11},
pages = {8185--8189},
numpages = {0},
year = {1992},
month = {Jun},
publisher = {American Physical Society},
doi = {10.1103/PhysRevA.45.8185},
url = {http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevA.45.8185}
}
@article{Dennis2002,
author = {Dennis, M R},
journal = {Optics Communications},
keywords = {c points,gaussian randomness,phase singularities,polarization,stokes parameters},
pages = {201--221},
title = {Polarization singularities in paraxial vector fields : morphology and statistics},
volume = {213},
year = {2002},
url = {http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0030401802020886}
}
と書かれてあったとします。もし、一番目の"Orbital angular momentum of light and the transformation of Laguerre-Gaussian laser modes"という論文を引用したい場合、その論文のidは"@article{"の直後にある"PhysRevA.45.8185"であるので、TeXファイルには
光渦は軌道角運動量$l$を持つ光のことを指し、
らせん状の等位相面やドーナツ型の強度分布などの特徴がある。
この光渦はアレンが1992年に最初に報告した\cite{PhysRevA.45.8185}。
出力結果(次の参考文献を表示するために必要な命令もお読みください)
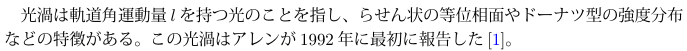
と書くことによって、出力結果のように、自動的に番号が振られ引用されます。
論文を引用した場合、卒論であれば最後の方に参考文献リストを載せなければなりません。ここでは、その方法について説明します。
まず卒論のTeXファイルのブリアンブルに
があるか確認してください。もしも、無い場合は、ブリアンブルにその内容を追加してください。(これは、natbib.styという参考文献用のスタイルファイルを利用して更に、引用した文献を番号で略記し引用した順に参考文献リストを作るという命令になっています。詳しくは、参考文献1を参照してください)そして、卒論のTeXファイルの一番最後(\end{document}直前)に
と書いてください。\bibliographystyle{unsrtnat}とはどのような形式で表示をするかを指定しており、ここでは、unsrtnat.bstを読み込むことを指示しています(詳しくは、参考文献1を参照してください)。そして次の行の\bibliography{bib}は「文献の情報としてbib.bibを読み込め」という意味の命令です。もしも、違う名前でbibファイルを作っているならば、{}の内容を適宜変えてください。(例えば、"abc.bib"というbibファイルを読み込ませたいのであれば\bibliography{abc}となります)また、\bibliography{bib,bib2,bib3}などカンマで区切ることにより、複数のbibファイルを読み込ませることも可能です。
参考文献リストには、読み込ませたbibファイルの内容のうち、本文中で引用されたもののみが表示されます。したがって、もしかしたら引用するかもしれない文献情報や今書いている文章では引用しない文献情報がbibファイルの中にあっても問題ありません、
最後にコンパイルの方法について説明します。文献番号と参考文献をきちんと表示するためには、(TeXworksでは)pdfpLaTeX→BibTeX→pdfpLaTeX(2回)の順でコンパイルをする必要があります。
図で説明すると、(TeXworksの左上の部分) →
→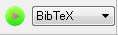 →
→ →
→ の順に再生ボタンを計4回押す必要がある。(最後の1回は不要の場合もあります。)
の順に再生ボタンを計4回押す必要がある。(最後の1回は不要の場合もあります。)
これにより、完成した参考文献リストは図4のようになります。