17年6月20日の活動
発想法を使ってみよう!:理論から実用へ
若手研究者による分野横断的な研究プロジェクトを実現するために,発想法の習得について皆で意見を出し合いながら学んでおります。現在まで、発想法のひとつであるKJ法の使い方について勉強してきました。今回はこのKJ法による“研究案の組み立て“という、より実践的な練習を行いました。
初めに、KJ法を用いた議論の方法、流れを廃棄物処分工学分野、岡田からスライドによる説明がありました。それに基づき、参加者で複数のグループを作り、それぞれで研究案を議論し、まとめる。主に以下の流れで議論を行っていきます。
 話題提供者:廃棄物処分工学分野 岡田
話題提供者:廃棄物処分工学分野 岡田
初めに、KJ法を用いた議論の方法、流れを廃棄物処分工学分野、岡田からスライドによる説明がありました。それに基づき、参加者で複数のグループを作り、それぞれで研究案を議論し、まとめる。主に以下の流れで議論を行っていきます。
 少人数でチームを結成→チームごとにKJ法を実行(キーワード列挙〜グルーピング〜議論 →提案されたテーマをチームごとに発表
少人数でチームを結成→チームごとにKJ法を実行(キーワード列挙〜グルーピング〜議論 →提案されたテーマをチームごとに発表 示された発想法の流れに基づき,KJ法を用いた発想法が実践されました。今回は3つのチームに結成。
示された発想法の流れに基づき,KJ法を用いた発想法が実践されました。今回は3つのチームに結成。 結成されたチームごとに創出された研究テーマが発表され,その新規性や独創性について議論されました。
結成されたチームごとに創出された研究テーマが発表され,その新規性や独創性について議論されました。
[活動風景のレポート]
まず、(1)各チームで自身の研究に関するキーワードを”ポストイット”という色つきの紙に何個も書き込んでいきます。次に(2)それぞれキーワードの書かれたポストイットを紙の上に並べ、関連するもの同士をグループ化します。最後に(3)グループ化されたものを元に研究テーマを議論していく(ポストイットは以下の写真参照)
3人ずつの少人数チームに分かれることで、お互い積極的に議論を行っていました。まず、お互いの研究内容を伝え合い、理解する点で非常に有意義だったと思います。各人が一生懸命自身の研究を説明し、相手の不明な点を質問する。異なる分野間で共通のテーマを見つけることは非常に難しいでしょう。今回のKJ法による練習でも研究面での関連性を見出すのは大変な作業でした。ただ、異なる研究間で“共通点を見出そう”という視点での議論そのものが非常に有意義にだったと感じました。
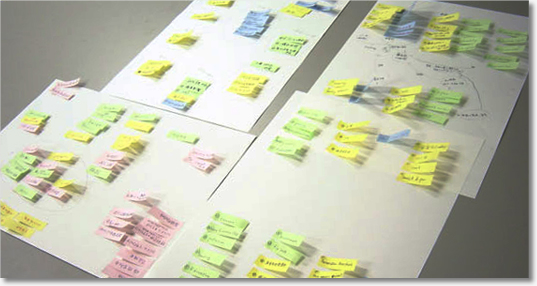
[議論した研究テーマ]
各チーム間で、おのおの研究テーマについて議論して頂きました。その内容をPowerPointファイルで載せておきます。若手研究会参加者の皆様、改めて中身を振り返ってみてはいかがでしょうか?
→ 研究テーマ6/20 (パワーポイントファイル:52KB)
まず、(1)各チームで自身の研究に関するキーワードを”ポストイット”という色つきの紙に何個も書き込んでいきます。次に(2)それぞれキーワードの書かれたポストイットを紙の上に並べ、関連するもの同士をグループ化します。最後に(3)グループ化されたものを元に研究テーマを議論していく(ポストイットは以下の写真参照)
3人ずつの少人数チームに分かれることで、お互い積極的に議論を行っていました。まず、お互いの研究内容を伝え合い、理解する点で非常に有意義だったと思います。各人が一生懸命自身の研究を説明し、相手の不明な点を質問する。異なる分野間で共通のテーマを見つけることは非常に難しいでしょう。今回のKJ法による練習でも研究面での関連性を見出すのは大変な作業でした。ただ、異なる研究間で“共通点を見出そう”という視点での議論そのものが非常に有意義にだったと感じました。
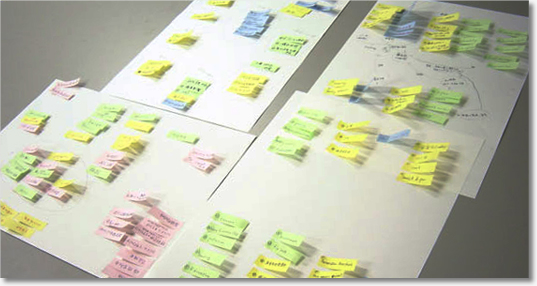
[議論した研究テーマ]
各チーム間で、おのおの研究テーマについて議論して頂きました。その内容をPowerPointファイルで載せておきます。若手研究会参加者の皆様、改めて中身を振り返ってみてはいかがでしょうか?
→ 研究テーマ6/20 (パワーポイントファイル:52KB)
