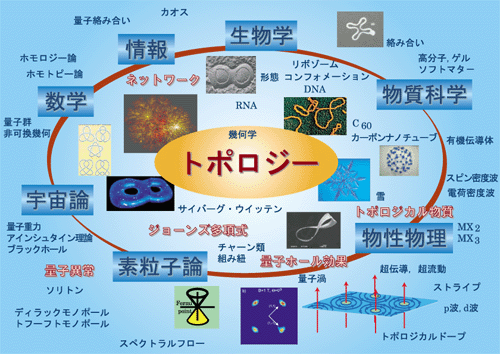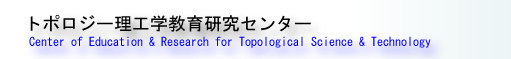センター長挨拶

センター長:丹田聡
本教育研究センターでは,トポロジーという「分野を横断して適用可能な普遍的概念」を切り口にした新領域・革新的学問分野を構築します.ともすれば専門的に陥りやすい数理科学・物理工学・計測情報工学・物質科学・生命科学・経済学の各分野を有機的に(まさにトポロジカルに)連携させることにより,世界的に例のない,基礎と応用の真の独創・学際的研究教育拠点の形成をめざします.そもそもトポロジーとは「柔らかいゴム膜を思い浮かべ,ちぎったり貼ったりせずに連続変形したときにも不変にのこる性質を探る」学問であり,幾何構造の連結性だけに注目し,その図形の本質的一面を追求する数学の一分野でした(19世紀後半).幾何構造一般を対象にしているため,初期の段階から,曲がった時空を表す一般相対性理論や場の量子論などの基礎物理分野において自然な形で利用されてきました.20世紀後半にはいり,トポロジカルなニ重螺旋構造をもつDNAや液晶・超伝導体におけるトポロジカル欠陥の発見に伴い,物性分野においてもトポロジーの概念が有用であることが再認識されてきました.さらに現在では,熱相転移や量子相転移などの臨界現象を扱う複雑系分野や,システムとしての関係性を重んじる生命科学,カーボンナノチューブ,各種ネットワーク,量子情報科学とも重要な関係があることが明らかになっています.それはまさにトポロジーが局所的な性質と大局的な性質の関連性を追及するという極めて一般的な科学的手法に関係する学問であるため,単に数学や物理学に留まらず,生物学・ネットワーク理論・情報理論・経済分野の切り口として必要とされているからです.
 それら多岐に渡る科学の分野を横断的・総合的に捉える試みはこれまでありませんでした.森羅万象の背後にある普遍則を追求する一手法として,トポロジーと力学を組み合わせて構造を規定するトポロジカル不変量を実験・現象論的に数量化し,最終的には理論的に誘導し,その帰結として得られる新しい原理を多くの科学の分野へ適用・応用していくことが本センターの大きな目的です.新しい学問体系を創成し,北海道大学から発信する所存です.
それら多岐に渡る科学の分野を横断的・総合的に捉える試みはこれまでありませんでした.森羅万象の背後にある普遍則を追求する一手法として,トポロジーと力学を組み合わせて構造を規定するトポロジカル不変量を実験・現象論的に数量化し,最終的には理論的に誘導し,その帰結として得られる新しい原理を多くの科学の分野へ適用・応用していくことが本センターの大きな目的です.新しい学問体系を創成し,北海道大学から発信する所存です.