若手研究者の活動 2
10月11-12日、若手シンポジウム、無事ソフトランディング!
 今年度始動時より若手同士の打ち合わせを重ね、頭に心に汗しながら練りに練った「若手の、若手による、若手のための」若手シンポジウムが10月11〜12日、若手会代表 堀さんの挨拶によって幕を開け、2日間にわたって開催されました。巣立っていったCOEのOBを国内外から招聘し、現役の若手RA、PDのみならず、教授、助教授など肩書きや国境などの垣根を越えたコミュニケーションと若手研究者のネットワーキングの基盤作りを実現しました。若手研究会の活動の一角が具体的な形として結実した最初のものであり、この成就は更なる若手研究者の活動の発展を予期させるものです。 今年度始動時より若手同士の打ち合わせを重ね、頭に心に汗しながら練りに練った「若手の、若手による、若手のための」若手シンポジウムが10月11〜12日、若手会代表 堀さんの挨拶によって幕を開け、2日間にわたって開催されました。巣立っていったCOEのOBを国内外から招聘し、現役の若手RA、PDのみならず、教授、助教授など肩書きや国境などの垣根を越えたコミュニケーションと若手研究者のネットワーキングの基盤作りを実現しました。若手研究会の活動の一角が具体的な形として結実した最初のものであり、この成就は更なる若手研究者の活動の発展を予期させるものです。 具体的内容としては、渡辺拠点リーダーの基調講演は、リーダーご自身の若手時代の苦労話、研究をどのように発展させてきたか、著名文献制作の裏話など、雲上の存在であった先生も始めから著名だったわけではないスタートラインがあったことを垣間見せてくれる貴重なお話をご披露いただけました。若手研究者は、リーダーに親近感を覚えるとともに、新ためて尊敬の念を濃くし、自分たちの未来へ向かう勇気や活力をいただいたことでしょう。 具体的内容としては、渡辺拠点リーダーの基調講演は、リーダーご自身の若手時代の苦労話、研究をどのように発展させてきたか、著名文献制作の裏話など、雲上の存在であった先生も始めから著名だったわけではないスタートラインがあったことを垣間見せてくれる貴重なお話をご披露いただけました。若手研究者は、リーダーに親近感を覚えるとともに、新ためて尊敬の念を濃くし、自分たちの未来へ向かう勇気や活力をいただいたことでしょう。また、広吉、佐藤(努)両助教授から、横断的共同研究の実例を紹介いただき、それに関わる実践的アドバイスや、失敗をチャンスに換える発想法、遂行上の障壁への対策、研究活動の楽しみ方などの情報提供ほか、発表後も若手研究者と活発に質疑応答で積極的に意見を交わす有効な場となりました。  COEのOB研究者は、現在の研究内容とCOE及び学生時代も含めた研究経緯を示しながら、研究者として異分野へ切り込むことの重要性を経験談を通して啓蒙し、現役若手COEの研究者にとって鮮度の高い内容だったと思われます。また、実際の問題点を提示しながらの現況報告は、未来の仕事の方向性に大きなヒントや希望を与えるものでした。 COEのOB研究者は、現在の研究内容とCOE及び学生時代も含めた研究経緯を示しながら、研究者として異分野へ切り込むことの重要性を経験談を通して啓蒙し、現役若手COEの研究者にとって鮮度の高い内容だったと思われます。また、実際の問題点を提示しながらの現況報告は、未来の仕事の方向性に大きなヒントや希望を与えるものでした。現役の研究成果発表は今回、グループ単位に分けるという、独自の形式をとり、時間の短縮化や聞き手の中だるみを軽減するために考案されたものです。内容が重複しないように工夫され、多少のスケジュールのズレも周到に対処し、スムーズな司会と供に、総合的にテンポよく発表されていました。 会場外でのポスターセッションでも多くの参加があり、また、2日目終了後の懇親会には拠点リーダーをはじめとする諸先生方にもご参加頂き、まさしくボーダーレスな和気藹々とした雰囲気の中研究者同士の親睦を深めることができました。 (取材:COE事務局 高橋筆)   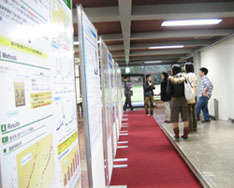
|
| >> 各者講評の要約 |
 |
シンポジウム運営スタッフとして 廃棄物処分工学研究室 博士課程3年 岡田敬志さん |
| 今回のシンポジウムに際し、補佐役として従事できたことは、非常に貴重な機会であったことを実感しています。この会の運営を通して、若手のコミュニケーションが確実に活発になったこと、またこれまで日常的に行ってきた活動の1つの集大成として示せたことに、大きな意義を感じます。 普段の若手研究会の活動自体でも様々な面において得るものが多かったです。具体的には、自分の研究で壁にぶち当たった時に若手会での情報交換が大きなヒントにつながったり、研究の方向性に疑問を抱いた時、若手会での意見交換が、検証していく助けになったという経験を得られたことです。 今回のシンポジウムでは、諸先生たちの貴重な経験談を聞くことができて、非常に参考になったので、今後もそのアドバイスを活かし、今後どんな環境で研究を続けるとしても、よい意味でリラックスして、臆せずアイディアをどんどん出せるように、また、研究者同士、活発に議論し、共同研究に積極的に取り組んでいきたいと考えています。 最後に、このシンポジウムの1番の賜物は、研究者同士の交流を深められたということに他なりません。今後もこの若手研究者のネットワークを大事に育て、活用して行きたいです。 |
 |
水代謝システムグループを代表して 環境フィールド工学専攻 沿岸海洋工学研究室 山下俊彦 教授 |
| 多忙のため、残念ながら、2日目の午前中しか参加することができず、非常に残念でしたが、こういった若手自身による企画・イベントはとても意義深いものだと思います。 したがって、恐縮ながらこの会自体の感想をあまり述べられないため、代わりに、私自身の共同研究の経験談をアドバイスとして、ここでお話させていただこうと思います。 私の携わった共同研究では、当初、異分野である水産フィールドの研究者との研究討議で、文化の違いを実感し、実質的な研究議論を深めて行くのに、労を攻したのは記憶に新しいことです。この時に、相手のニーズや論点をあせらず、時間をかけて理解していくことが重要であると感じたので、若手研究者の皆さんも同じような事態に直面した際に、スタート時点議論がかみ合わないことがあったとしても、状況に屈することなく、おおらかに構え、時間と回を重ねることで必ず、実りある議論を交わせ、研究を実現できることを信じてがんばっていただきたいと思います。 |
 |
廃棄物代謝システムグループを代表して 環境循環システム専攻 資源再生工学研究室 恒川昌美 教授 (廃棄物代謝グループリーダー) |
| 諸先生方にも発表いただけた有意義な会であったと思いますので、私の「講評」は「好評」ということです!初めてPD,RA若手研究者自身の手によって、ここまでの会にできたことは賞賛、評価できるものです。今後もこれを自信にして、研究活動など益々活発にがんばっていただきたいと思います。 COEの目的の1つとして、「国際的に活躍できる若手の育成」が掲げられているので、このように若手が活躍する場としての若手研究会が発足したことは非常に喜ばしいことです。COEスタート時点、このタイトルに対して手閑でしたが、当研究室の伊藤助手の提案を私が後押しする形でスタートしたこの若手研究会がこのように順調に成長しているのを見るにつけ非常に頼もしく思っております。 渡辺リーダーは、狭い領域、国、企業などの組織も飛び越え偉業を成し遂げられてきていますが、私は科学領域を越えた「笑い学」の領域でも活躍してきました(笑)。つまり、領域を超えて活躍する研究者は際立つということをお話ししたいわけです。例えば、8大学のドクターコースの学生を集めたプロジェクトでも、自分の頭で考えて実行し、結果をフィードバックでき、かつリーダーシップ、コミュニケーション力がある学生を輩出することを目的としています。このことから、有能な若手研究者の育成つまり領域を超えた研究をリードし成し遂げることができる研究者の育成が「技術立国日本」再興においていかに重要であるかお分かりいただけるかと思います。 したがって、この有意義な若手研究会の活動を今後も継続し、今回築いた若手研究者同士のネットワークをより強化し、活用していくことは非常に重要になります。そして、それを礎に北大の世界における存在感を維持、推進していただきたいと思います。 |
 |
社会基盤施設管理システムグループを代表して 環境創生工学専攻 維持管理システム工学研究室 佐藤靖彦 助教授 |
| 今回のシンポジウムは、若手がゼロから立ち上げ成し遂げたということ自体が非常に価値あることだと思います。たとえば,普段若手が行っている研究というのは、指導教官など先生たちのベースからスタートします。 研究とシンポジウムとをひとくくりにはできませんが,今回のように自分たちがゼロから組み立て上げるという経験は、とても貴重です。今回の経験は、今後の皆さんの成長に大きな影響を与えるに違いありません。 具体的な各グループの成果発表については、全般的にグループ内であまりディスカッションされていない印象を受けました。ただ、廃棄物代謝グループの堀さんや岡田さんの発表については、共同研究を誘発させるようにキーワードの提示があり、他研究者へ働きかける意欲が感じられました。それ以外の発表については、もう一工夫し、より高いレベルを目指してほしいと思います。 今私たちのこのCOEには、3つのグループの融合が求められています。その意味においても今回の取り組みは非常に価値あるものです。私もまだ若手だと思っています。一緒に努力していきましょう。 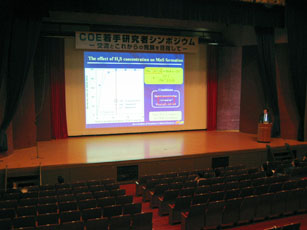
|
<< 前へ │ 次へ >>
