|
(1) AHPの理論と実際、木下栄蔵編著、実際編pp.259-268執筆、日科技連(2000) ~株式会社日科技連出版社ホームページより~  【主要内容】 【主要内容】21世紀を目前にして、混迷を深める現代社会において、「意思決定」というキーワードがますます重要になってきています。それは、様々な条件が錯綜する中から、最も重要な戦略的目標を達成するために最適な選択を効率良く行う必要が高まってきているからです。このような時、新しい意思決定手法として登場してきたのがAHP(階層分析法)です。AHPの新しさは、経験や勘という感覚情報を意思決定のプロセスにおける重要な要素にしているところにあります。これにより、従来の手法ではモデル化できなかったり、数量化することが困難であったテーマも、AHPを使うことによって、扱うことが可能となりました。本書は、AHPとその発展形ANP(ネットワーク型分析法)の理論解説、および10編の適用事例を収録した、AHPに関する書籍の決定版です。 【主要目次】 (理論編) 第1章 序論 第2章 AHPからANPへ 第3章 支配型AHPと一斉法 第4章 集団合意形成とAHP 第5章 整合性とファジィ性 第6章 AHPと効用関数 第7章 AHPと固有値問題 (実際編):10事例 グループAHPによる人事評価への適用/AHP評価の繰返し修正支援法とその実装システム/感覚情報の定量化による機械システムの信頼性・安全性解析/絶対評価法によるリニューアルのコストベネフィット評価/国際的適用事例とソフトウェア/阪神高速道路における自動点検監視システムの評価/新たな地方国際空港の候補地選定/ANPモデルによるリスク評価(執筆担当)/21世紀の社会経済環境の構造変化に対応したトリップ発生モデル/県民意識調査と県の将来像の評価 (2) 参加型社会の決め方-公共事業における集団意思決定-、木下栄蔵・高野伸栄共編、pp.197-210(7.4 ファジィAHP)執筆、近代科学社(2004) 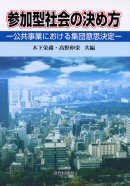 ~近代科学社ブックストアより~ ~近代科学社ブックストアより~近年、公共事業に対する批判が高まり、その声は国民の空気になりつつあります。それらの批判は謙虚に受け止めなければなりませんが、一方で都市部の社会インフラが国際競争力を失っているのも事実です。 そこで、公正で有効な社会インフラを整備するためには新しいパラダイムを確立する必要があります。それは1990年からの失われた10年強を総括し、その以前のパラダイムから新しいパラダイムへの創造を意味します。すなわち、一言でいえばオペレーショナルマネジメントから戦略的マネジメントへの変更です。 このようなパラダイムに従えば、公共事業採択(優先順位)は代替案の創造と意思決定手法により評価される必要性が認められます。我々はこれまで、以上の用件を念頭に置き、公共事業におけるPI、市民参加型ワークショップの運営などで生じる現実的課題と集団意思決定理論(合意形成モデル)との位置づけを模索し、モデルの応用の可能性と現実的課題の解決のために必要とされる理論研究の方向性について議論を重ねてきました。 本書は、以上のような経緯を経て生まれたもので、種々の分野で「意思決定」を研究・勉強されている研究者や学生、実際の業務で「意思決定」解析等に従事されている人たちのためにわかりやすくまとめたものです。 詳しくはこちら (3)バスサービスハンドブック、土木学会土木計画学研究委員会規制緩和後におけるバスサービスに関する研究小委員会編集、第Ⅲ編5.1(p.361)、5.4(pp.374-379)執筆、土木学会(2006)  ~土木学会ホームページより~ わが国においては、高齢社会の進展やバス市場の規制緩和などの社会変化の中で、どのようにバスサービスを計画すればよいのかが様々な地域における共通の課題となっています。 本書では、バスサービスを計画するための基本的な考え方や手順、技術を体系的に整理したものであり、地方自治体の担当者,コンサルタントの技術者など、バスサービスを計画するすべての方に有益な内容となっています。 なお、この分野における研究は現在も進行中であり、また、計画に係わる制度にも変化が見られます。それらの動向を踏まえて、今後も内容を改訂していく予定です。 |
|
Copyright (C) 2009 Kunihiro KISHI. All Rights Reserved |