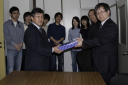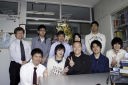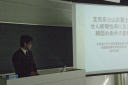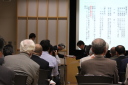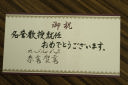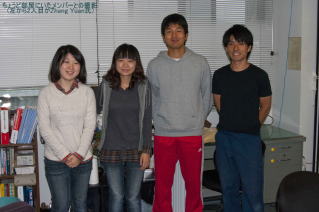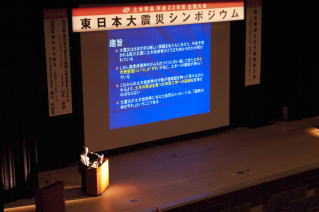| 2016�N4��7���`13�� | |||
| ����28�N�x�I�[�v�����{���J�Â���܂��B | |||
|
|||
| 2016�N2��27�� | |||
| �X�l�N���k��̐��E�W�J�͋������Ɣh����i���V�A�j��Best Scientific Research����܂��܂����B | |||
|
|||
| 2016�N2��25�� | |||
| ���^���N�ƐԒˑ��Y�N������27�N�x�n�ՍH�w��k�C���x����(�w������)����܂��܂����B | |||
|
|||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
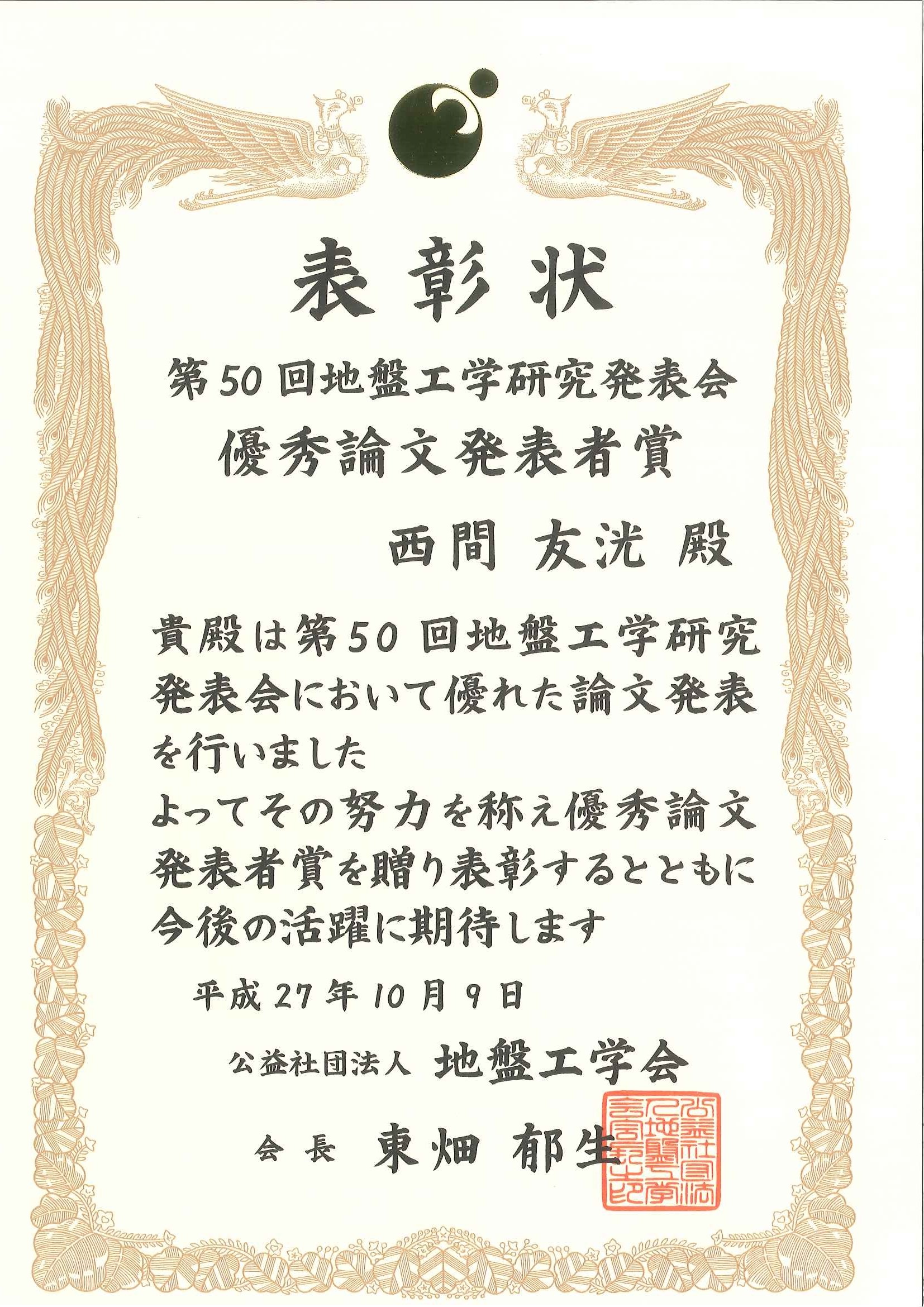




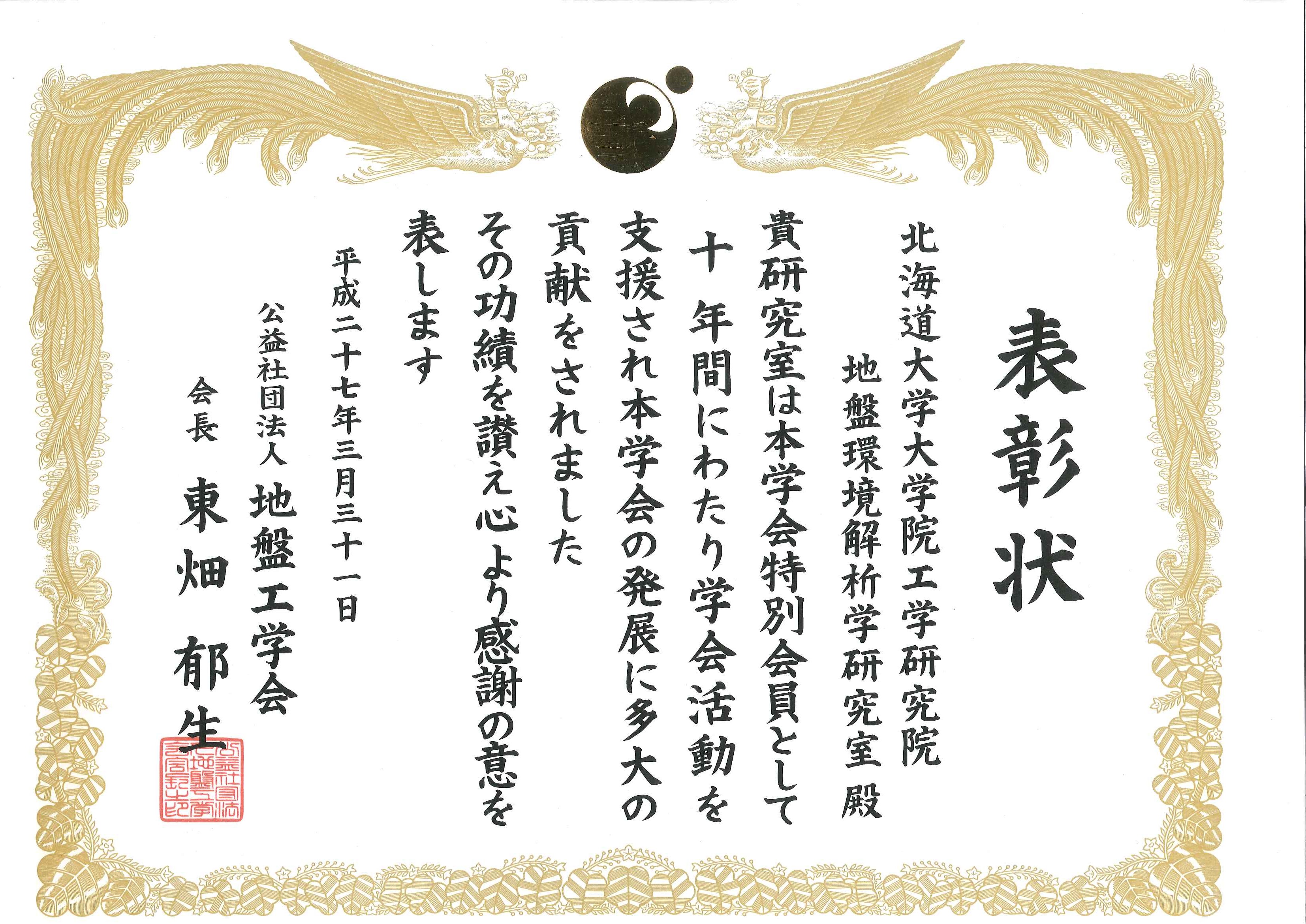


 �@�@
�@�@
 �@
�@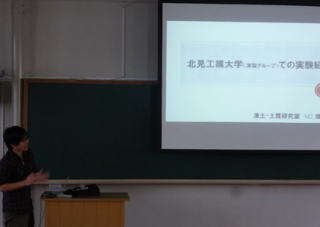
 �@
�@
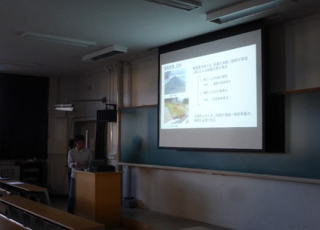 �@
�@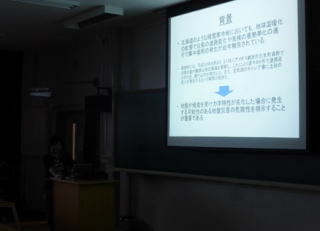
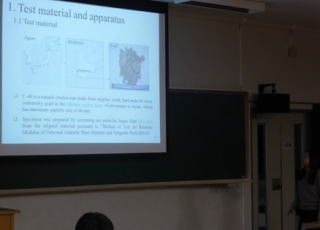 �@
�@